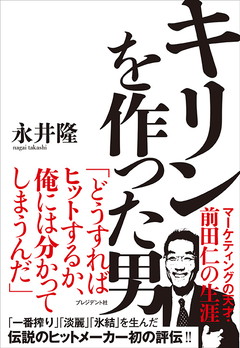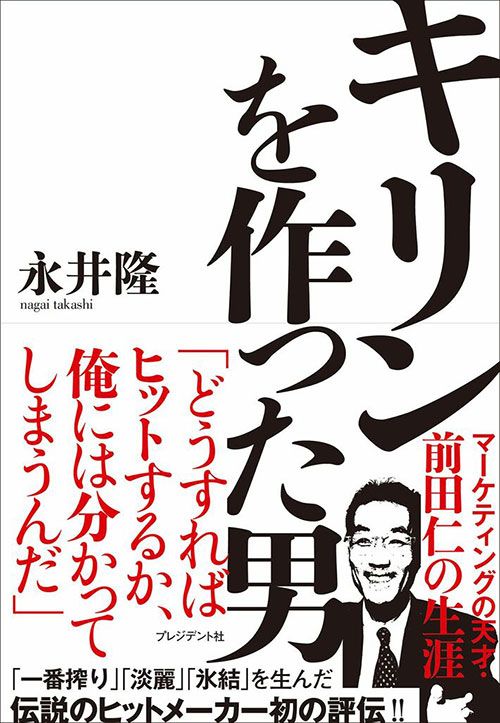※本稿は、永井隆『キリンを作った男』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。
生産現場からの反発
「一番搾り麦汁だけを使うビールを、前田チームが開発している」
そのニュースが駆けめぐると、たちまちキリン社内から反応があった。ただその大半は懐疑的、批判的な反応だった。
「君は、何のためにマーケティング部にいるのか、わかっているのか」
工場長や生産部門の幹部が集まる、全国工場長会議に呼ばれた舟渡知彦は、年輩の工場長からいきなりこう質されたという。
「スーパードライに対抗する大型商品を作り、多くのお客様に喜んでもらうためです」
直近まで名古屋工場醸造課に勤務していた舟渡は、すかさずそう反論しようとした。まるでビジネス小説の主人公のように。
だが、現実はそう格好よくはいかない。大先輩の前で、若い舟渡は「はい……」と返事をするのがやっとだった。
すると工場長は勢いづいて語気を荒げた。
「こういう無茶な商品開発をマーケティング部の連中にやらせないために、君を送り込んでいるんだ! 君が率先して生産現場を苦しめてどうするんだ!」
別の工場長が続ける。
「仕込み係は二番搾り麦汁の最後の一滴まで、それこそ搾り取るように採っている。君は去年まで名古屋工場にいたんだから、その苦労がわかるはずだ」
麦汁の一滴は血の一滴
その工場長の発言は間違いではなかった。ポタッ、ポタッ、としたたり落ちる滴だって、年間を通して集めればかなりの量になる。
日本はビールの酒税が高いため、ビール会社の利益は薄い。ビール業界には「麦汁の一滴は血の一滴」という表現があるくらい、麦汁は無駄にしてはならないという考え方が染み込んでいる。「一番搾り」案に、工場が反発するのは当然だった。
工場に比べると、本社の生産部門の役員や幹部の反応は、比較的冷静だった。ただ、前田のプランに理解を示してくれるほどではなかった。
というのも、本社生産部門の役員や幹部はみな、「スーパードライ」の脅威を実感していた。
「思い切った商品を作らなければ、スーパードライを止められない」
という考えが、共通認識として行きわたっていた。
一方、工場は現場しか見えていなかった。いかに効率よく生産するか、1円でも2円でもどうやってコストダウンするか。それが彼らの仕事のすべてだった。商戦の激化や、ライバル社の商品の大ヒットよりも、内側に目が行きがちだった。
舟渡はその温度差に接し、少なからぬ戸惑いを覚えたという。ただ、この時の彼はもう工場の醸造技術者ではない。マーケティング部所属で前田仁の部下という立場だ。
舟渡は前田についていくほかなかった。