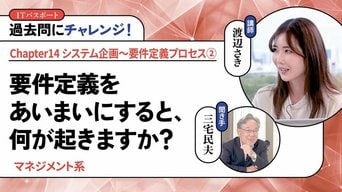支援員の女性とひきこもり男性を訪ねる
住所の書かれたメモを片手に、坂道をひたすら上る。さっきから吹き出す汗が止まらない。ワイシャツはもう汗だくだった。熱海特有の急坂を、自分の足で上ってみようと思い立ったことを後悔せずにはいられない。
商店は海沿いに集中しているため、山の中腹に住む人は、車がなければ買い物に出かけるのもひと苦労だろう。私は一人、自宅にひきこもっている男性のもとを訪ねるべく、くねくねした蛇のような山道をひたすら上り続けていた。
男性の自宅は、ごく普通の一軒家だった。バブル期に区画整備された住宅街にあり、建物自体も一目でしっかりしたつくりだとわかる。この日の取材については、石橋さん(注:筆者が出会った、ひきこもりの支援員)が事前に電話で了解を得てくれていたので、早速インターホンを鳴らす。
現れたのは、眼鏡をかけた実直そうな男性だった。「ああ、どうぞ。上がってください」遠慮がちな口調で、迎えてくれた。伊藤茂夫さん(仮名)は、60歳になったばかりだという。
身長は180センチ以上あり大柄だったが、少し猫背で、どこか気弱そうな印象を受けた。家のなかはとてもきれいだった。床に出しっぱなしのものは一つもなく、掃除も行き届いている。几帳面な方なのだろう。
「お金がなくなったら死ぬからほっとけ」
リビングに通され、伊藤さんと机を挟んで向かい合うと、私は思わず「きれいな部屋ですね」と口にしてしまった。伊藤さんは、「そうですか?」とはにかみながら、「気になるんですよね。散らかっていたり、中途半端な状態でものが出ているのとかが」と性格的なものだと教えてくれた。
伊藤さんは7年間、自宅にひきこもっていた。支援を受け始めたのはつい先月のことだった。石橋さんは、伊藤さんを紹介するときに、こんなことを言っていた。
「伊藤さんには最初、『何しに来たんだ、お前ら』って怒鳴られました。『お金がなくなったら死ぬからほっとけ』って。確かに、お金が尽きたら生活保護を受けるよりも、ご自身で命を絶つという選択をする人は少なくないんです。だから、お金がなくなったら死ぬんじゃなくて、なんとか手に入れようって思ってくれないものですかねって、何度も通って話したんです」
「お金がなくなったら、死ぬ」──。伊藤さんはなぜ、助けを求めずに死のうと思っていたのか。その理由が知りたかった。なかなか切り出しにくい話ではあったので、持参したバナナ型の手土産を渡し、雑談をしながらタイミングを待った。