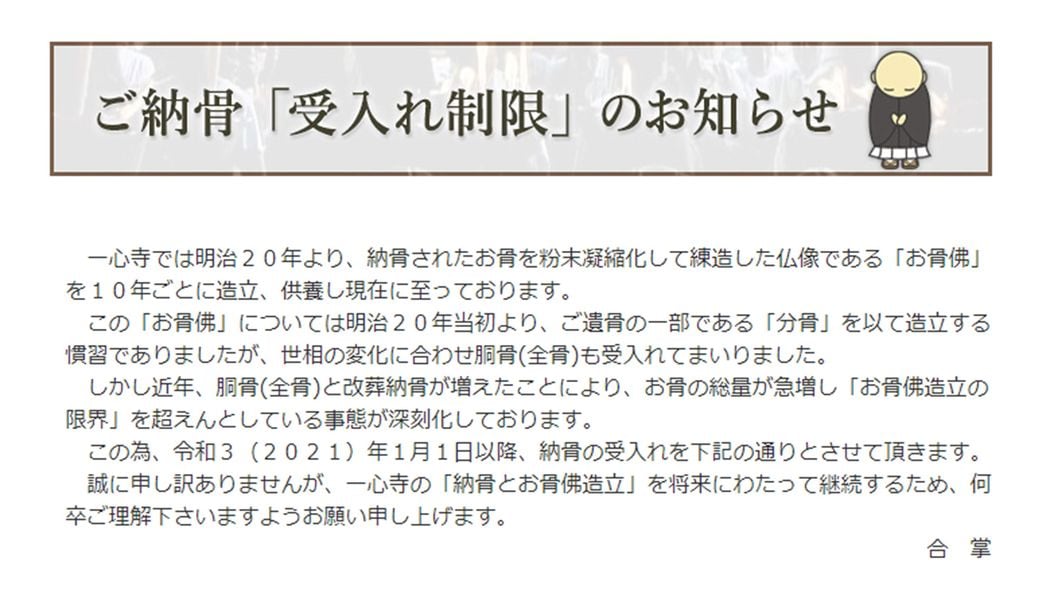多くの寺院経営は厳しいのに「納骨受け入れ制限」する理由
今月、ある新聞広告が目についた。広告主は、大阪市天王寺区にある一心寺という浄土宗寺院である。宗教法人が墓地分譲などの新聞広告を出すことは珍しくはないが、この広告は真逆であった。来年2021年以降、納骨の受け入れを制限するというものだ。
私は「いよいよ、そうせざるを得ない状況になってきたのか」と、複雑な心境になった。背景には、昨今の改葬や墓じまいの増加がある。
これだけを聞けば「墓じまいが進み、足元の寺院経営は厳しいはずなのに、納骨受け入れ制限というのはどういうことか」と、疑問に思う人も少なくないだろう。
だが、一心寺は特殊な事情を抱え、常に世相を反映してきた寺院なのである。本稿では、世にも珍しい一心寺の葬送の形態と、現代人の葬送の変化を見ていきたい。
遺骨でつくった「お骨仏(おこつぼとけ)の寺」
一心寺は遺骨でつくった「お骨仏の寺」として知られている。
開基されたのは、1185(文治元)年のこと。もとは近くの四天王寺の付属の草庵であったが、江戸時代に入り、徳川家康の八男・仙千代が夭折した際に当時の住職が葬儀を執り行ったことがきっかけで家康の庇護を受けた。慶長年間の大坂冬の陣の際には、大阪城からちょうど1里離れたこの一心寺が徳川側の茶臼山本陣となった。幕藩体制下では寺社奉行直轄の檀家を持たない特別寺院に位置づけられる。だが、幕末になって衰退し、一心寺はなんらかの収益源を模索することになる。
そこで庶民向けに無縁の精霊を供養する施餓鬼供養を始めると、大いに評判になった。
幕末から明治初期にかけて、地方から大阪に丁稚奉公に出てきた次男坊らが、この地で定住しはじめた。すると、遠い故郷の菩提寺に祀られているご先祖様を、大阪で供養したい、とのニーズが高まる。
そこで大阪の庶民は「一心寺なら宗派を問わず供養してくれる」と、分骨した遺骨を持ち寄るようになった。評判が評判を呼び、続々と一心寺に遺骨が集まり出した。1868年から1888年までの20年間で、境内の納骨堂は満杯になってしまったという。
そこで、当時の住職が考案したのが、遺骨を仏像に造形し、お祀りすることだった。人骨を粉砕し、鋳型で固めて阿弥陀如来像にする。こうすることで、大阪に拠点をもつ分家筋が、いつ何時でも手を合わせることができる。そのうえ永久的に、時代を超えて大勢の参拝客が、手を合わせてくれる。
現在、永代供養墓はどこの寺でもあるが、その元祖が一心寺の骨仏なのである。