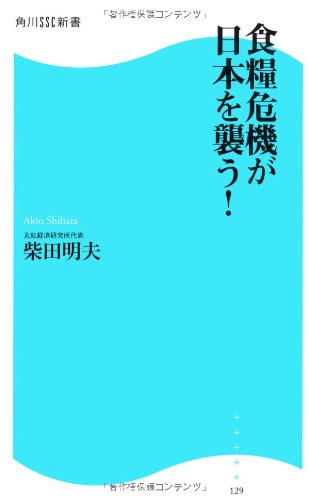若い頃から中国国内各地を歩きまわっていた私にとって、一番好きな原風景は蘇州から南京へ行く途中の田園風景だ。まさに、いくら見ても見飽きない山水画そのものだった。しかし、1980年代後半「世界の工場」となったこの一帯は、コンクリートの工場棟が緑の田園を蝕み、覆い隠してしまった。もう車窓の風景を見ることもなく、いつしか、山水画のような風景も思い出さなくなった。だが本書を読んだときにその風景が一気に蘇った。
「農業を疎かにする国は滅びる」「多くの経済大国は食糧生産大国でもある」。著者が指摘するように、主要な経済大国の食料自給率は高い。米国は128%とトップを走るが、フランスも122%と負けてはいない。ドイツは84%で、日本の半分以下の人口の英国も70%と日本を大きく引き離している。データは2003年のものであるが、十分な重みを持つ。
10年に、日本がGDP世界2位という座を中国に渡してしまった原因は中国の追い込みにあったのではなく、農業大国になりえなかった日本の宿命的な運命だろうと私は思う。著者が指摘したように、日本でカロリーベースの食料自給率は79年に約80%あったのに、今や40%台まで激減してきた。それに合わせたかのように耕作を放棄された土地も夥しくある。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント