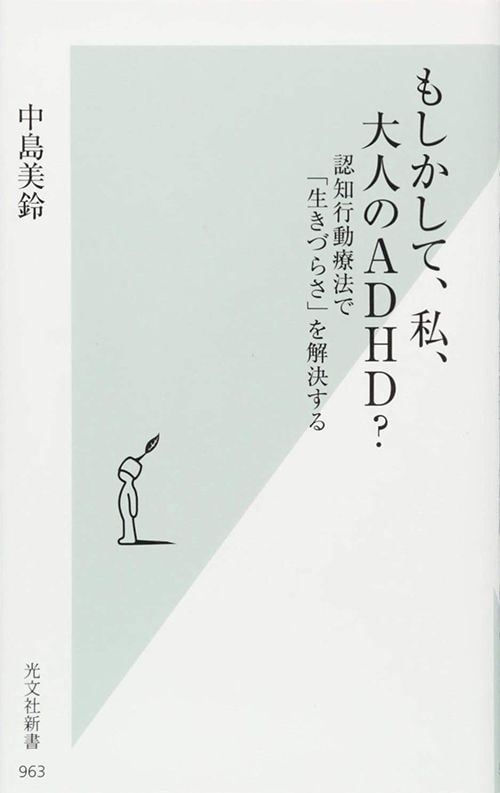「私は、ほかの子と違う」
ミサさんは、小さいときから「私は、ほかの子と違う」という思いを抱えて過ごしてきました。
小学生のころのミサさんは、ほかの女の子が身の周りをきれいに整えていて、忘れ物もなくきちんとしているのに、自分だけがいつもプリントをなくし、ハンカチを忘れてしまいます。授業は退屈でたまらず、教室の中を歩き回ることはしませんが、いつも頭の中は空想でいっぱいでした。もしもこうだったら、ああだったら、と頭の中を常に忙しくしていないと、じっと座っていられませんでした。
当時は、みんなそんなものだと思っていましたが、大人になってから周囲に聞いてみると、そんなに四六時中いろいろ考えごとをしていないと気が済まないのは自分くらいでした。
中学生のときに家庭訪問に来た担任の先生が、家でのミサさんと学校でのミサさんの姿があまりに違うことに驚いたのだそうです。ミサさんの部屋は、足の踏み場もないほど散らかっていました。ミサさんはそのことでよく母親に叱られていましたが、結局、部屋を片づけるのは母親で、学校への提出物は、心配した母親が毎日、口酸っぱく注意をし、鞄の中を点検していてくれたおかげで遅れずに提出できていました。
生活態度を親から注意されても、なかなか改善できず、いつも「言っても身につかない」とあきれられていました。学校の成績は優秀で、大きな問題を起こすことはありませんでしたが、学生時代のミサさんは、「社会人になるのが怖い」と思っていました。
危機感への共感を得られない
実際、ミサさんは社会人になってからも、自分ひとりで朝起きて、支度をして、決められた時間までに出社するということが非常に苦手でした。これは大学生になったときに初めて実感したことですが、これまでは親元で暮らしていたので、そうしたことが明るみに出なかっただけであり、ミサさんは生活のリズムに大きな問題を抱えていました。
仕事に対しても、同じことの繰り返しで飽きてしまうのではないか、うんざりして辞めたくなるのではないかと心配していました。ミサさんは学生時代にアルバイトをいくつか経験しましたが、どのアルバイトも1カ月もすると、行く前にどうしようもないくらい気分がどんよりして、やる気が起きず、どれもあまり長続きしませんでした。
結婚は、もっと心配でした。今だって朝ご飯も食べずにバタバタと飛び起きて仕事に出かけているのに、家族のために毎朝ご飯をつくることができるとはとても考えられなかったと言います。ただでさえ絶対無理と思っていることが、一生続くと思っただけでめまいがしそうでした。