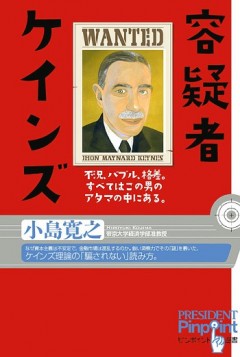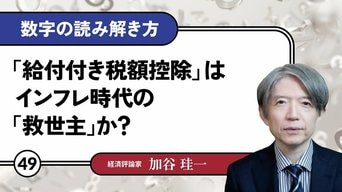乗数効果についてのケインズのロジックをもう少し、詳しく見よう。
ケインズは、経済規模が有効需要すなわち企業の投資需要と家計の消費需要の和の水準に一致するように決まる、と論じた。また、家計の消費需要は家計の貯蓄額に依存して決まり、その家計の貯蓄額自体は企業の投資額と一致するのだから、結局は経済の規模は企業の投資額で決まる、とした。
したがって、政府が公共事業を行って生産物の利用者になるなら、それは投資需要の増加と同じ効果を持つはずである。つまり、政府が公共事業を行い、例えば2兆円分の財の需要を余計に生み出すなら、それが有効需要に加わることで、ちょうど2兆円分の財が増産され、それは生産に携わった国民の所得になるから、国民所得も2兆円増え、懐が暖まり、景気もよくなる、というわけである。
財政政策によって、生産量と国民の所得の増加を促し、景気を下支えする、というケインズのこの考えは広く受け入れられ、20世紀中盤から後半にかけて、多くの国がこのような方針を採用した。そしてこのことは、特有の社会問題を引き起こすこととなってしまった。それは、政治家や官僚の腐敗、そして、深刻な環境破壊である。
財政政策は、道路を造ったりダムや河口堰を作ったりなど、環境に負荷をかけるような事業の形態をとることが一般的であった。それは、そもそも景気対策としての公共事業が民間産業の妨害をしないよう配慮しなければならないことから、民間の着手しにくい事業を選択しやすいこと、それと、失業者を専門的な教育なしに即時的に雇用し得る部門が土建部門である、ということの帰結であった。そして、このような公共事業は、政治家や官僚に大きな経済権力を与えることになり、あまたの汚職事件や収賄事件を生じさせることになったのである。
他方、経済学者の間では、このような公共事業による景気対策という方法論の有効性が疑問視されるようになっていった。中でも、2006年に大阪大学の小野善康が発表した論文「乗数効果の誤謬」は、そのような反論の中で決定的なものであった(とぼくには思える)。
小野の議論を大胆にまとめるなら、「乗数効果は、国民の所得を増やすという意味での景気対策には全く効果を持たず、また、その実質的効果は政府が投じた金額ではなく、作られた公共物の価値に依存する」というものである。つまり、政府が税金から2兆円を使って公共事業を行っても、国全体の生産物は2兆円分増えるわけではなく、作られた公共物の実質的価値が半分の1兆円なら、1兆円分しか増えない、ということである。次回、この小野の主張をぼくなりの解釈によって説明しよう。
●この連載は、小島寛之著『容疑者ケインズ』の第1章の一部、ケインズの「一般理論」の批判的解説を転載したものです。