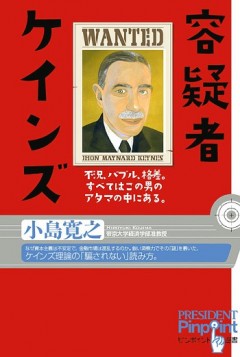前回みたように、小野善康の研究によって、ケインズの乗数効果はとどめを刺されてしまったように思われる。つまり、政府が公共事業を行ったからといって、それが国民の所得を増加させ、景気を浮上させるわけでない、ということだ。国民の可処分所得に変化はなく、誰の私的所有物でもない公共物が生まれるだけで、しかもそれが額面通りの価値を持つ保証もないのである。
だがここに、この乗数効果を救済する道が1つだけ残されている。このことは、ケインズの『一般理論』の中でも最後の「覚え書き」の中で触れられており、小野も前掲の論文とは別の小野自身の不況理論の中でこれと同じ効果を指摘している。それは、国内における経済格差の存在に注目し、その格差を理論の中に持ち込むことである。
結論を先にいうなら、失業者の経済行動をケインズの仮定する家計部門の経済行動原理から引き離せば、ケインズのいいたかった乗数効果が再論証されるのである。具体的にいうと、失業者たちが、貯蓄を持たず、また、納税からも免れていると仮定すれば、ケインズのいう乗数効果は幻ではなくなる。すなわち、公共事業は確かに国民の可処分所得を増加させ、また私企業の生産も増加させるのである。以下、それを詳しく解説しよう。
今、完全に失業している国民たちは、ケインズの仮定(2)からはずれた経済行動をするとしよう。すなわち、所得がいくらであろうが、決して貯蓄はせず、すべて消費に使う、と仮定するのである。さらには、完全失業状態から雇われた労働者は所得から税金を徴収されない、とも仮定しよう。するとどうなるだろうか。
ここでも、前の設定を踏襲する。つまり、民間企業が500兆円の生産を行い、そこで生産された財の400兆円分は家計によって消費され、残る100兆円分が、貯蓄によって金融市場から企業に提供され、企業は100兆円分の財を設備投資に利用する。
このとき、500兆円分の財の生産では、国民の望む労働量全部をカバーすることはできず、国民の一部が失業してしまっている。ここで次期に政府が、失業者以外の国民から2兆円の税金を徴収して、失業者を雇い、2兆円分の公共事業を執り行った。次期の経済は、どうなるだろうか。