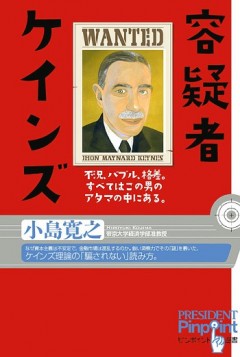一見、ケインズの乗数効果のロジックは説得的に見える。ところが厳密に考えてみると、ケインズの考えには深刻な飛躍があることが見て取れる。それは、ケインズのロジックが現実の経済と整合的か、という実証的な問題以前に、乗数効果という考えがケインズの理論の仕組みそのものとの間でさえ深刻な論理的矛盾をきたしている、ということである。ケインズ自身が、自分の理論の仕組みの中で、混乱し錯誤している、ということなのだ。
注目すべきは国民の「可処分所得」である。
可処分所得とは、税金を納めたあとに手もとに残る所得のことだ。実は、国民の可処分所得は公共事業がなされたからといって全く増えないことがわかる。つまり、政府が公共事業を行わないときの国民の所得(=消費額+貯蓄額)と、税金を2兆円徴収して公共事業をし、その報酬を国民に支払うときの可処分所得は、全く変わらないのだ。
それはあたりまえである。
なぜなら、ケインズの仮定では、家計部門の消費と貯蓄は一方が決まれば他方も決まることになっている。企業部門の投資額が変わらないのだから、家計部門の貯蓄額もその投資額と一致したまま変わらない。だから、消費額も公共事業がないときの水準と同じままでなければならない。ここで前と状況が変わるのは、政府によって2兆円の税金が徴収されることである。したがって、納税前の所得が前より2兆円増えていなければ、消費がその分減ることになって、ケインズの仮定に矛盾してしまう。つまり、納税前の所得は確かに2兆円増える。しかし、これを税金として納めてしまえば、国民の手もとに残る可処分所得は前と同じ水準であり、そういう意味で国民の私的な経済水準は全く同じままなのである。つまり、景気など全くよくはならないのだ。
それを理解した上で考えるべきなのは、経済パフォーマンスを測る上で適切なのは、納税前の所得なのか、それとも可処分所得なのか、という点だ。そのためには、納税前の所得で増加した2兆円とは、いったいどういう存在か、ということを丹念に考えるべきだろう。
この疑問に答えるには、前にしたように、生産物とお金の流れを表に出すのが有効である。
以下、イメージしやすくするため、具体的設定を追加しよう。政府が公共事業を行わないときの企業の投資需要を100兆円とし、そのとき家計部門の貯蓄額は当然100兆円であるが(「投資と貯蓄の均等原理」)、貯蓄額が100兆円のときの家計消費の総額は、仮に400兆円に決まる、と仮定して話をすすめる。この場合、企業部門の財の生産は500兆円ということになり、これはそのまま国民全員の所得額となっている。