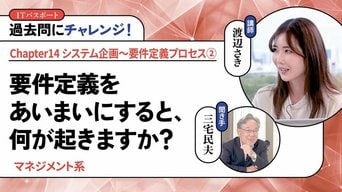戦後史の謎として最大級のものの一つが、日本と台湾の関係の深さである。日本が公式には国交を持たない台湾(中華民国)は、それでも自由民主党に人脈の網の目を張り巡らせ、言論界にも大勢のファンを抱えている。そのような日台関係の急所に切り込み、各界の熱心な台湾ファンの心情の原点にたどり着いたのが本書だ。
その原点とは、第二次大戦終了時の中華民国の指導者だった蒋介石の演説「以徳報怨(徳を以て怨みに報いる)」だ(実際には、蒋はこの通りの発言はしていない)。戦争で日中は敵国同士だったが、戦後は恨みっこなしで、新たに友好関係を築こうという寛大な姿勢を打ち出したのである。
これには多くの日本人が感激した。だが、蒋介石はルーズベルトやチャーチル、スターリンを向こうに回して自分の戦略目標を追求した大政治家である。善良な一般の日本人には、その真意は想像もつかなかった。1949年に共産党との内戦に敗れて台湾に逃げ込んだ後の蒋は、ちっぽけな島から大陸への反攻を本気で目指していたのだ。彼にとっては日本も日本人も、その目的を達成するための道具でしかなかった。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント