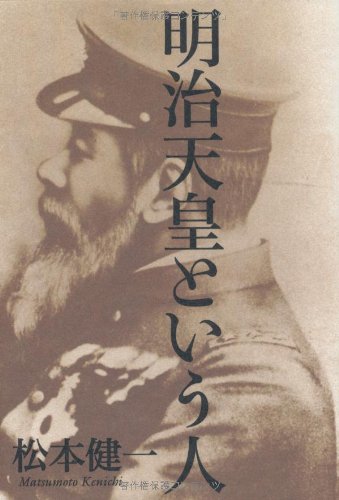『アーネスト・サトウ日記抄』を読むと、最後の将軍となった徳川(一橋)慶喜について、激動の時代を動かしていた人々の慶喜評が記されている。
「将軍慶喜の動止を視るに、果断勇決、志望また小ならざる様(略)軽視すべからざる一の頸敵と存じ候」(岩倉具視)
「一橋胆略決して侮るべからず。若もしいまにして朝政挽回の機を失い、幕府に先を制せられることあらば、じつに家康の再生を見るが如し」(桂小五郎)

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント