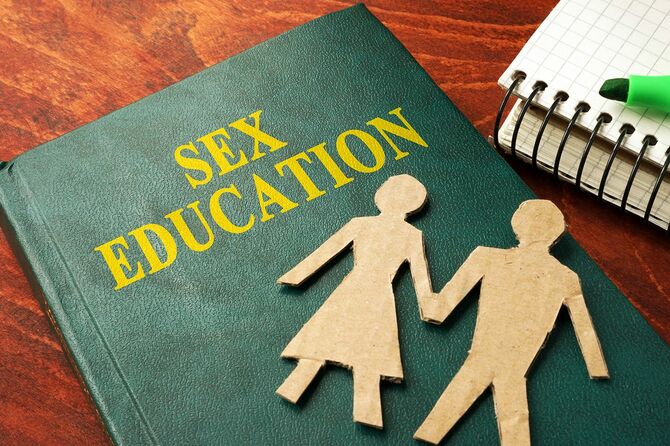家庭も学校も「性教育」を嫌がる
性教育映画はトレンドとなり、映画スターたちは、性教育に後ろ向きな家庭や学校に代わって国民に性や生殖に関する正確な知識を広める急先鋒になった。
「僕はドナー」以来、ありとあらゆる性や生殖に関する映画が作られるようになった。従来のインド映画では、妊娠や出産の場面は生々しい映像や話題になりがちなので、そそくさとやり過ごされることが大半であった。
新婚の女性が嘔吐し、妊娠が告げられ、妊婦の10カ月はソングシーンなどでそそくさと語られて、一瞬だけ分娩中の女性の苦しい顔が映し出され、次の瞬間には赤ちゃんの泣き声が響く、というのがパターン化された妊娠・出産の描き方であった。

ここから先は無料会員限定です。
無料会員登録で今すぐ全文が読めます。
プレジデントオンライン無料会員の4つの特典
- 30秒で世の中の話題と動きがチェックできる限定メルマガ配信
- 約5万本の無料会員記事が閲覧可能
- 記事を印刷して資料やアーカイブとして利用可能
- 記事をブックマーク可能