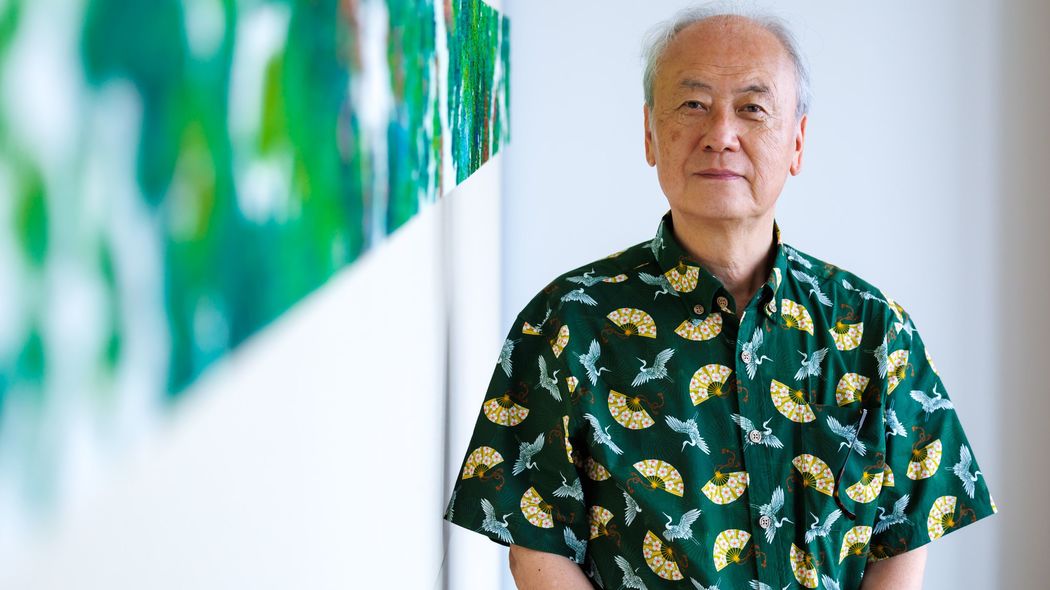「日本語」が日本社会の構造的な特徴を支えている
さて、ここまでの議論に登場した、天皇を頂点とする「垂直的な階層構造」や、上位者に価値が集中する「権力の偏重」、そして被抑圧者が抑圧者に豹変する「抑圧移譲」といった現象は、われわれが常日頃漠然と感じていることと、大きく相違するものではないだろう。多くの人が、「そう言われればそうだな」という感想を持つのではないだろうか。
ところが、『日本語に生まれること、フランス語を生きること』には、まさに目からウロコが落ちるような斬新で、衝撃的な指摘があるのだ。上記のような日本社会の構造的な特徴を支えているのは、他ならぬ、日本語だというのである。
これはいったい、どういう意味だろうか。
【水林】たとえばぼくが、岸田文雄氏に面会したとして、ぼくはいったい彼のことをどう呼ぶでしょうか。
まさか「岸田」と呼び捨てにすることは問題外ですし、「岸田さん」もありえない。二人称の人称代名詞「アナタ」を使うことすらできない。結局、「総理」と肩書きで呼ぶことになるのでしょうか(※編注)。
※取材は2024年8月に行われた。
「二人称の人称代名詞」を相手との関係で使い分ける
【水林】この時、いったい何が起きているかと言えば、「首相」に対しては、「キミ」も「オマエ」も「アナタ」もだめで、「総理は」とか「岸田首相は」という選択しかありないということは、日本語がぼくにそのように命令しているということです。話し手の自由にはならない。
一方、フランス語では、相手が首相だろうと大臣だろうと大富豪だろうと、二人称の人称代名詞は基本的にvous(ヴ)しかありません。英語でいえばyouに当たる、vous以外に呼びようがないのです。
では、日本人はいったいどういう基準で二人称の人称代名詞を使い分けているのかといえば、相手との上下関係、強弱関係によって使いわけているわけです。
たとえば、いまここにメロンがあるとします。フランス語だったら「これはメロンです=C’est un melon」としか言いようがありませんが、日本語の場合、「これはメロンです」「これはメロンでございます」「これはメロンだ」「これはメロンだろ」などと、複数の言い方が可能ですね。もうひとつ別の例を引きましょう。漱石の『吾輩は猫である』をフランス語に訳すとJe suis un chat(英語ならI am a cat)としか訳せません。実際、仏訳版ではそのように訳されています。ところが逆に、Je suis un chatを日本語に訳すとなると「吾輩は猫である」は可能な翻訳のひとつに過ぎないことに気づきます。「わたしは猫である」「わしは猫である」「わたしは猫です」「ぼくは猫です」「俺は猫である」「俺様は猫だぞ」などなど、いろいろ考えられるからです。
そして、どの使い方を選択するかは、ひとえに相手(=対話者・二人称)と自分の関係を話し手がどう意識しているか、つまり「相手が誰なのか」にかかっているのです。日本語が「二人称的世界」であるといえるのは、この特異な現象をとらえてのことです。森有正の話をする時がきたようですね。