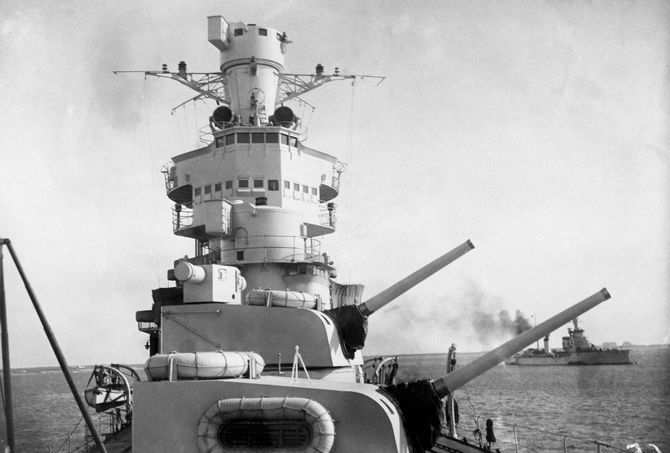まぶたはおっ開いたまま、閉じることはなかった
けれども江南の体はつめたく冷えていくばかりだった。その顔はげっそりこけて、鼻のあたりがいやにとがってきた。皮膚の色も、急に血の気がひいて、白く透きとおったように青ざめてきた。だが、それはどう見てもおだやかな死顔じゃなかった。糸切歯をのぞかせて片方にひきつれている口もとには、殴られた瞬間の苦痛がそのまま凍りついている。
それからその目はどうだろう。両方ともまぶたがめくれあがって、びっくりしたようにおっ開いたままだ。自分はどうしてこんなことになったのか、自分でもわけがわからないとでもいうようなけげんな目つきで、どこか遠くのほうを見つめている。
その目は、看護兵がいくら指でおさえてやっても、どうしてもふさがらなかった。
おれたちは、江南に白の二種軍装を着せてやった。これは彼が、おれといっしょに播磨に転勤してきたとき着てきた軍服である。軍服は、彼の体にまるで合っていなかった。上衣もズボンもだぶだぶで、どうしたって、子供に軍服を着せたとしか思えない。
中元兵長は泣いているように見えた
野瀬兵長は、江南の腕から時計をはずしてやりながら、しきりに目をこすっていた。山岸は震え通しで、ろくろく手が動かなかった。
着がえがすむと、看護兵は脱脂綿をちぎって江南の鼻と口につめ、顔に二つ折りにした白いガーゼをかぶせた。そして、そのときになってはじめて、江南の死がなまなましい実感となって、おれにせまってきた。
おれは、頭がへんにくらくらして、これ以上ここにいるのが耐えられなかった。
するとそこへ分隊長が戻ってきて、班長だけ残ってあとはすぐ帰るように言った。まもなく副長や軍医長、衛兵司令たちが検視にやってくるのである。それを聞くと野瀬兵長は救われたようにあわてて部屋を出ていった。彼もきっといたたまれなかったにちがいない。おれも山岸といっしょに、急いで江南の衣類をまとめると、それをもって、左舷の通路に近いとなりの医務室のほうへ出ていった。
見ると医務室の隅のところに、中元兵長が向うむきに立っている。片桐分隊士も先任下士官も来ていて、彼は二人からいろいろ事情を聞かれているらしい。顔をふせたまま石のように固くなってうなだれている。ときどき手で鼻のあたりをこすっているところをみると、あるいは泣いているのかもしれない。