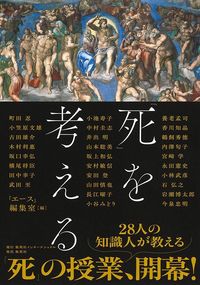シニアの存在が集団を強くし、人間の寿命が徐々に延伸
人間はどうでしょうか。
人間は他の大型霊長類と違ってなぜか体毛が抜けてしまい、さらには木にも登れなくなりました。それぞれが弱いので、生き残るためには皆で協力する必要がありました。人間が他の霊長類よりも長生きになったのは、長生きする方がその集団の力が強くなったから。つまり、シニアがいい仕事をしたのです。
例えば、この見方で一番有名なのが「おばあちゃん仮説」。チンパンジーなどの場合、体に毛が生えているので、生まれてすぐにお母さんにしがみつけます。つまり、お母さんは子どもがいても両手が空くのです。でも人間の場合は、生まれて2~3年は誰かが抱っこしたり、ついていたりしなければいけないですよね。そういうときに親以外で誰が頼りになるかといえば、祖父母。おじいちゃん、おばあちゃんが面倒を見てくれる方が、親に余裕ができて圧倒的に子沢山になる、という理論です。加えて、若い人だけの集団よりもシニアがいる集団の方が、話がまとまる。若い頃は生きるための欲に満ち溢れていますが、シニアになるとそういうことから解放されてきて、人のために何かしようと思うようになるからかもしれません。
ゴリラやチンパンジーのメスは死ぬまで生理があるし、オスも死ぬまで生殖しますから、人間のような利他的な存在にはなりません。彼らの中にシニアはいないのです。生物としては、生殖に関わらなくなった個体がいるのはほぼ人間だけ。これもまた変化と選択で、たまたま生殖機能を失っても生きている人が出てくるようになり、そういう人には孫がたくさんできた、それが長寿化の原因の一つになっていったということなのだと思います。
人間の寿命は社会によって決まります。その社会が何を選択するかによって進化の方向は変わるのです。昔は集団(コミュニティー)を大切にしたためにこういう進化を遂げてきたけれど、今はどうでしょう? コミュニティーに属さなくても基本的には生きていけますから、今後の人間が違う進化の道筋をたどる可能性は十分あると考えられます。(以下、後編に続く)