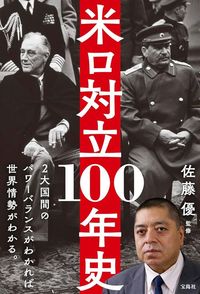ウクライナで被害が深刻だった大飢饉
農業集団化に伴う1930年代には大飢饉が起きた。餓死者は推定約400万~600万人。とくに被害が深刻だったのがウクライナで、農産物や家畜を政府に奪われた人々は、木の根や野生の獣などあらゆる食糧を探し、なんと人肉食に手を染めた者までいたという。この苦い記憶は、21世紀の現在まで続くウクライナ人のロシアへの強い反発心の一因になっている。
また、富農と並んで弾圧されたのが教会だ。聖職者は共産主義の敵と見なされ、次々と処刑や流刑の対象となった。1931年12月には、モスクワにあったロシア正教会モスクワ総主教に属していた救世主ハリストス大聖堂が政府によって爆破された。
ソ連共産党は、救世主ハリストス大聖堂の跡地に、ソヴィエト宮殿という巨大なビルを建設する計画を立てた。そのコンペにはスイス出身のル・コルビュジエを筆頭に、海外の著名な建築家が大量に参加しており、当時は海外にもソ連を支持する知識人が多かったことを反映している。ソヴィエト宮殿の構想は壮大で、頂上部に高さ75メートルのレーニン像を置き、全高415メートルもの超高層建築を予定していた。アメリカで1931年に竣工した当時世界最大の建築物であるエンパイア・ステート・ビル(102階、381メートル)を上回る高さだ。ここにもアメリカへの強い対抗意識がうかがえるが、その後の第二次世界大戦の勃発により、ソヴィエト宮殿は建設途上で放棄され、計画は撤回された。
1930年代のソ連は「アメリカに追い付け、追い越せ」
このほかにも、1930年代のソ連には産業や文化のさまざまな分野で、「アメリカに追い付け、追い越せ」という意識が漂っている。ソ連では、映画もまた国民の娯楽だけでなく、政治宣伝の手段だった。渡米経験をもつ映画監督グリゴリー・アレクサンドロフは、チャップリンの出演作をはじめとするハリウッド映画の手法を取り入れ、『陽気な連中』『サーカス』などのヒット作品を生み出した。ソ連共産党政治局員で食料供給と貿易を担当したアナスタス・ミコヤンは、アメリカで食べたソーセージとアイスクリームをソ連でも生産できるように、アメリカ製の機械を備えた食品工場を次々と建設した。政治思想では敵対していても、ソ連にとってアメリカは「憧れの国」だった。