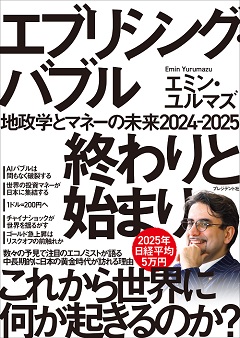ベトナムでは米国の存在が大きくなっている
また、ベトナムにとって外交上重要な国として、昔からロシアが最上位にあり、それと同じところに、社会主義国である中国が入っているが、実は近年、米国のステータスが引き上げられ、ロシアや中国とほぼ同じ位置づけになってきた。それだけ、ベトナムにとっては米国の存在が大きくなってきたということだ。
とくに米国は、デカップリングで中国をグローバルサプライチェーンから外した時の代替地として、ベトナムを重視しているように思える。米国の半導体企業などは、ベトナムに研究センターをつくったりもしているのだ。
現在のベトナムは人口が多く、人口構成で見ても若い世代の人口比が非常に高い。高度経済成長期の日本と同じような感じだ。インフラも整っているし、なによりも労働コストがまだ安い。
一人あたりGDPは、今のところ4000ドル程度。だから、まだプライベートな交通手段といえばバイクが中心だが、一人あたりGDPが1万ドルを超えてくると、自動車が一気に普及し始める。まさにそこへ向かって経済成長を続けている。
米国がデカップリング政策によって本格的に中国を切り離せば、次の注目国はベトナムになるだろう。
「迂回先」として存在感を高めるメキシコ
さて、ここまで米中新冷戦と、それに関連の深い地域ということで、東アジア、中東を中心に地政学リスクを考えてきたが、少し場所を変えてみたい。中南米は、果たして米中新冷戦の影響を受けるのか。
地理的には中国からきわめて遠く、領土・領海問題とは無縁の地だ。
ただ、中南米はその名の通り、米国とは地続きの関係にある。そのため、経済的には米国にきわめて近い。
まずメキシコだ。米国にとっては隣国であり、1846年から1848年にかけて、テキサスの帰属をめぐって両国は戦争を行った。ちなみに今のカリフォルニア州はもともとメキシコの領土だったが、この戦争で米国が勝利を収めたことにより、米国の領土になった。
このような歴史を経て、今は米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)が締結されている。これは、米国、メキシコ、カナダの間で結ばれている自由貿易協定だ。この協定の元は、1994年に発効した北米自由貿易協定(NAFTA)であり、この協定締結はメキシコにとって追い風になると思われていたが、現状、実際にそのようになっている。