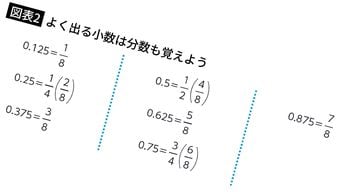やっと公表された「セクシー田中さん」の報告書
昨年10月~12月に日本テレビ(以下、日テレ)が放送したドラマ「セクシー田中さん」の原作者・芦原妃名子氏が亡くなった問題で、日テレと原作マンガの版元だった小学館がそれぞれ調査報告書を公表した。
日テレの報告書は5月31日に公表された。当初はゴールデンウィーク明けくらいに公表されるのではないかと言われていたが、結果的にずいぶん時間がかかった印象だ。
私は事前にマスコミ各社から公表後のコメントやインタビュー取材を打診されていた。それらの記事をネットや新聞でお読みになった方もいらっしゃると思うが、紙幅の都合でコメントの一部しか紹介されていない。
そして6月3日、こんどは小学館側が調査報告書を公表した。本稿では、これら両社の報告書を比較考察したうえで、私なりの分析を論考として述べたい。「なぜ不幸な事件が起きてしまったのか」というプレジデントオンラインに寄稿した最初の問いをさらに掘り下げる。
今回の報告書を検証する視点は、大きく分けて以下の3点である。
①初見の感想、全体の印象はどうだったか/「現場の作り手」から観て共感できるものだったのか
②調査の姿勢はどうか/「踏み込み」の度合いや方法は適切か
③報告書の「今後に向けた提言」は再発防止に資するものなのか/私が過去にプレジデントオンラインで指摘した「ドラマ多産化現象」「コミュニケーションの断絶」といった原因に切り込めているか、もしそれが不十分であるとすれば、なぜそうなってしまったのか
日テレの報告書で目立った「自己防衛」
この問題の経緯を簡単に整理したい。
報告書によると、日テレは昨年2月末~3月、原作マンガを連載していた小学館にドラマ化を提案した。小学館は芦原氏の要望として「原作マンガに忠実に表現すること」などを求めたが、日テレ側は「強い要求」と認識せず、食い違いが生じたという。その後もその食い違いは是正されることなく、改変やドラマ終盤の展開などをめぐり、芦原氏の不信感が増大していった。
そして1~8話を担当した脚本家の相沢友子氏が降板し、9話、最終話を芦原氏が急遽担当することになった。放送終了後の昨年12月末、脚本家がSNSで不満を投稿。芦原氏も今年1月にこの経緯を投稿していた。SNSでは脚本家や日テレへの批判が高まり、芦原氏は「ごめんなさい」と投稿した翌日、栃木県内で亡くなった。
ここから本題に入ろう。視点①「初見の感想、全体の印象はどうだったか/『現場の作り手』から観て共感できるものだったのか」についてだが、時間をかけて丁寧に調査をおこないそつなくまとめているが、本当に「制作現場」のことを考えた内容になっているのかという点においては疑問が残る。以下に理由を述べる。
日テレの報告書は様々な人々にアンケートやヒアリングを実施している点において、評価に値する。アンケートは71人、ヒアリングは39人とのことだが、そのうち外部の意見がどれくらい反映されたかが気になった。
なお小学館の社内調査は「関係者へのヒアリングをおこなった」としているが、その規模や人数は触れられていない。