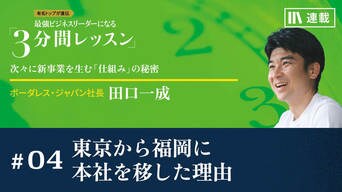4位 コスパ・タイパの悪い行動
「Z世代はコスパやタイパを重視する」「映画はストーリーを知ったうえで早送りで観る」
ネットのニュースでそれを知り、“老害”認定されたくないと、コスパやタイパを過剰に気にするようになった昭和世代もいるかもしれない。だが、コスパ、タイパの悪いことを長らくやってきた人が、今さらZ世代と同じ土俵で勝負できるのか?
徹夜のカラオケ。年賀状や暑中見舞い。ローカル線の旅。図書館で調べ物をした時間。人気のチケットを入手するためにリダイヤルを続けた体験。待ち合わせ時間に相手が来なくて募らせたセンチメンタルな気持ち。レンタルビデオ店でAVだけ借りるのは恥ずかしく一緒に借りたどうでもいい映画……。それらを「コスパやタイパが悪い」と切り捨てていいのだろうか?
そんな一見無駄なことが、今の自分を形成してきたと考えられないだろうか。むしろ、Z世代が持っていない財産といえるのではないか。
デジタル化など社会の新しいシステムについていく必要はあるだろう。しかし、今後もZ世代が避けるコスパ・タイパの悪いことからも学び、そこから何かを得ることができるのは、昭和世代特有のスキルだと考えようではないか。
5位 先輩・後輩で深い関係性を築く
現代の一部の企業では、社内のフラット化、風通しのいい環境づくり、実力主義の実現のために、「さん付け」を徹底し、上下関係を撤廃しようとする動きがある。長らく日本の企業で当たり前だった年功序列は、過去のものになりつつあるのだ。
昭和の日本では中学・高校・大学の運動部などで、先輩が後輩に対して権威主義的な、時には暴力的な支配を行うことがあった。それに似た傾向のある職場も多く、「ウチは体育会系なんで」などと自慢げに話す人もいた。
しかし、厳しすぎる上下関係は、パワハラやブラック体質を生む要因となりうる。そうした面からも、「後輩は先輩に無条件に従うべきだ」という考え方は不健全といえよう。
だが、両者に良好な関係性が築けているのなら、先輩・後輩というつながりは決して悪いものではない。たとえば、悩みや困りごとがある人が、自分より経験値の高い人に助言を求めることは自然なことだろう。かつて先輩に酒や食事を奢ってもらった人が、今度は自分の後輩に奢る。そこに伴う喜びは、決して悪いものではない。
だからこそ、コンプライアンス重視のテレビのドラマでも、先輩・後輩は理想的な人間関係のパターンとして今も頻繁に扱われがちなのである。
6位 社員旅行、運動会、草野球など社内レクリエーションを活用する
昭和の企業では、社員旅行、運動会、はたまた野球大会などの社内レクリエーションへの参加は、半ば強制的なものだった。
そしてそれは、パワハラ、セクハラの温床となるケースも多々あった。たとえば、社員旅行での大宴会では女性社員に酒をつぐ役割が求められることが多かった。また、アルコールが苦手な人の立場はとても軽視されていた。
00年代以降、働き方の多様化、プライベートと仕事の境界線の明確化もあり、「若者の社員旅行離れ」が進み、全国的に実施件数が激減したのは自然な流れだったろう。
ところが近年は、平成生まれのベンチャー企業などが社員旅行や運動会を積極的に行う例が目立っている。ワンマン経営者の自己満足である可能性はゼロではないが、少なくともそうした企業が昭和式で行っているとは考えにくい。社内運動会の企画運営を請け負う専門業者まで存在するほどだ。
自由参加でハラスメント要素ナシ、かつコミュニケーションの円滑化手段として機能しているなら、そこに不適切要素を探し出すのは難しい。また、そうしたレクリエーションの場は、部下が上司の、上司が部下の実像を見極める場としても価値があるかもしれない。各自が普段、職場では見せない顔を見せることもあるからだ。