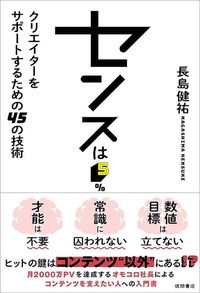「自分が出したゴミはしっかり片付けること(糞尿含む)。」
ルール化することの弊害もたまにあります。
以前、男性のトイレでうんこが流れていないことがありました。これに対して「うんこ流してください!」と全員宛にアナウンスしたのですが、「うんこを流さなきゃダメというルールってあるんですか?」と反論してきたメンバーがいました。たしかにこれはルールに書いていなかったので怒ることはできませんでした。
ルールを作ると穴をついてくる人は必ずいます。ルールを作るのであれば、しっかり網羅的に制定しないとと思いました。また、これ以来「自分が出したゴミはしっかり片付けること(糞尿含む)。」という一文を追加しました。
「加湿器vs.除湿機を見たい」と言われたらどうするか
ルールを作る弊害として「ルールをハックするやつ」というのが必ず出現します。
僕はメンバーとの付き合いが長く特性もわりと知っているので、ルールを作る際は「こういうツッコミが入りそうだな」といったことも想定して作るようにしています。
最近も弊社が運営しているメディアのラジオで、僕が聞いていないと思ってか「今は引っ越ししたてで稟議がざるになってるから今のうちいっぱい稟議出したほうがいい」といった事を言ってたり、「加湿器がほしい!」と言った社員に対して、たしかに乾燥していたということもあって、かなり大きな加湿器を購入して設置したら、そこの近くにいた別の社員が「除湿機がほしいです! 加湿器の前に置いて戦わせたいです」とわけのわからないことを言ってきたり、ほうぼうからよくわからない意見がとんできます。
ルールを立てるときには、ツッコミどころを意識してたくさんの目線を組み入れて設計しています。が、「加湿器vs.除湿機を見たいので除湿機を購入してほしい」といった想定外の申請も来るわけです。
こういうときはどうしているか。定量的、定性的両軸のバランスを見ながら判断するようにしています。
例えば加湿器であれば一般的な推奨湿度などがあるのでそこを指標に置きつつ、執務スペースの実際の数値を計測して定量的に判断していきます。「空気が乾いている」というのは個人によっても感覚の差があるので全員の意見を聞くわけにもいきません。自分の感覚に頼りすぎないように注意します。
定性的にというと、「これを導入したらビビるだろうな」「盛り上がるだろうな」という感じを意識しています。例えば今回に関していうと「除湿機を導入する」です。きっと一部のメンバーは盛り上がると思います。ただ、この定性判断はとても難しく、結局は個人の感覚によるものですし、仮に除湿機を導入して加湿器と戦わせてもすぐ飽きるのは目に見えています。定性的すぎるのはよくありませんが、いずれのバランスも大事にしています。
もちろん他にも大切なことはありますが、最低限守りたいルールさえ作っておけば、どんなにブレてしまったとしても会社として立て直しが利くので、不安はないと思います。ルールは自由になるためでもありますし、元の場所に戻ってこられる安心感を得るために作るものでもあると、僕は考えています。