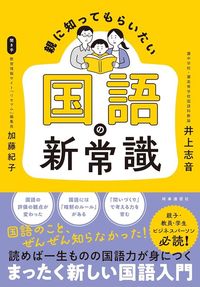現代文学を読みたいが現場には時間がない
【加藤】子どもが「あなたはどう思ったの?」と聞かれて、自分が思ったことを答えたときに、「そういう見方もあるよね」と言われると自信や自己肯定感につながるのは、国語の授業ならではですよね。アートなども同じです。そのように、自分がどう感じたかを認めてもらえる授業って、一部の子どもたちにとってはすごく大切な居場所だと思うのですが、いかがですか。
【井上】それは大きいですね。一方で、その裏返しで、「もしも自分の感じ方がほかの人に共感されなかったらどうしよう」という恐怖心や不安感も子どもたちにはあるのかもしれません。日本ではどちらかというと、「みんなと違ってもいい」ではなくて、「みんなと一緒がいい」という感覚が根強くあります。違うことを思っていたとしても、一緒に染めてしまうようなところがありますから。
【加藤】同調圧力の問題ですね。それにしても、高校の新しい学習指導要領は、国語の先生たちの間では不評なのではありませんか?
【井上】文学ができない国語ってなんだろう、という話にはなりますね。古文も文学かもしれませんが、やはり現代文学ならではの学びがあるはずです。本当は取り組みたいのに、現場には時間がありません。
「役に立たないから読まない」
【加藤】私は「本屋大賞」の作品が好きで、最近ですと、2021年本屋大賞受賞作、町田そのこさんの『52ヘルツのクジラたち』(中央公論新社)を読んだときは3回くらい号泣しました。
現代の作家さんたちは社会の縮図を見事に切り取って文章にしていると思うのですね。ですから、子どものころからこのような作品を読んでほしいのですが、「そんなの読んで何かの役に立つの?」という子どもが多いように感じます。
【井上】「文学を読んでも役に立たない」という考え方がありますよね。この場合の「役に立つ」とは、どのような視点で言っているんだろうと思うのですが。そもそも、実用性を重視して文学を読むことなどありません。でも、文学作品を鏡にして「自分」の実像を考えるという経験は皆さんもお持ちだと思います。
【加藤】映画やテレビ、ネットの動画などとは異なる没入感みたいなものが文学の醍醐味です。でも、多くの子どもたちがそれを体験しないまま大人になってしまう。