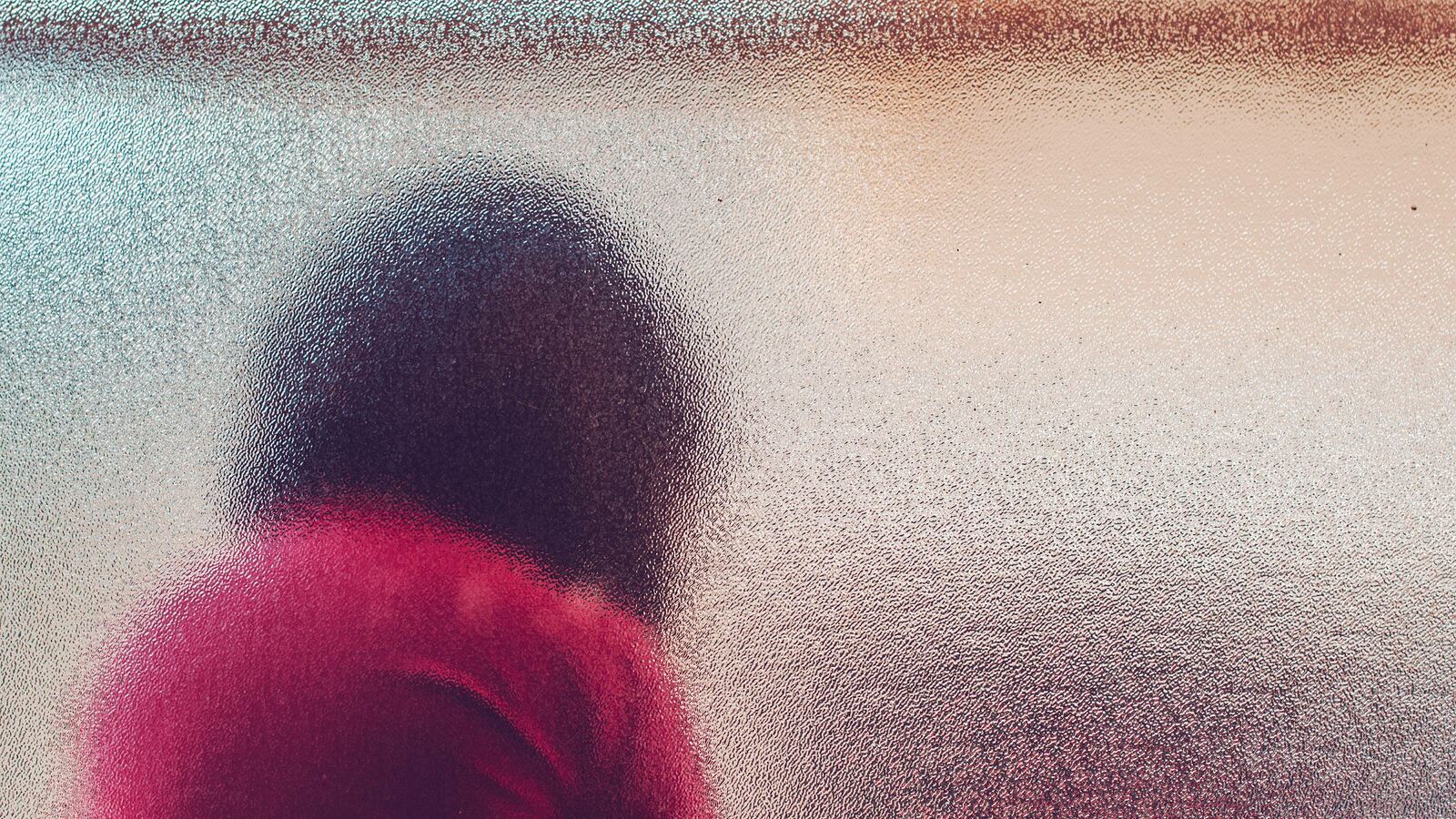※本稿は、菅野久美子『母を捨てる』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。
生涯にわたって私を束縛した母の言葉
私が4歳のとき、弟が生まれた。母のお腹が日に日に大きくなっていくのを横目で見ながら、私は子ども心に、どこか不穏なものを嗅ぎ取っていた気がする。身重になった母は、自分のお腹を撫でさする時間が増え、それはとても愛おしそうだった。
そしてほどなくして、衝撃的な事件が起きた。
びっくりするほど小さくて頻繁に奇声を発する、へんてこな生き物が私の前に突如として現れたのだ。それは生まれたばかりの弟だった。母は、そのへんな生き物を愛おしそうに腕に抱き、頬ずりした。いつもと違う様子に感じた胸騒ぎを、私は今でも覚えている。そして、それは的中した。
そのときから母の関心は、がらりと変わった。どんなに私が「お母さん」と言っても、かまってもらえず、無視される。いつからか母の口からは「お姉ちゃんなんだから」という言葉が、しょっちゅう飛び出すようになった。その言葉は生涯にわたって、私を束縛した。
弟が生まれて、私は透明人間になった
確かに弟は可愛かった。それは一般的な男の子よりも中性的だったからだ。
弟は今でこそ背が高くなり、がっちりした男らしさがある男性になったが、生まれたときから3歳くらいまでは目がくりくりとした、まるで「女の子のような」容姿をしていた。
そんな弟は、近所でも評判の子どもだった。
弟はベビーカーに乗っていても、中年の女性たちからいたるところで声をかけられた。「あの子、女の子みたいね。あら、男の子だって」「かわいいね」。そんなとき、母はまんざらでもないという顔で、笑顔を振りまいた。私はそのベビーカーの後ろをただただ、存在を消してついていくしかなかった。
母にとっては、弟はとにかく何よりの自慢の種だった。母は、弟が生まれてから、私を意図的にいないものとして扱うようになった。けっして忙しいからではない。私という存在を徹底的に無視するようになったのだ。どんなに母を呼んでも、甘えても、目を向けてもらえない。返事もしてもらえない。そんなことが増えはじめた。
まるで私は透明人間だった。弟が生まれてからというもの、そうやって母からネグレクトされる日々がぐんと多くなっていた。母の乳房も、愛情も、すべて弟のものになった。それは、私の自尊心をズタズタにした。