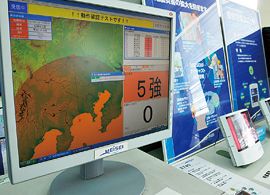大小問わず、危機に瀕している国内電気機器メーカー。裏腹な「ものづくり礼賛」の風潮にどこか違和感を覚える今、北関東の片隅にある社員300人の“凄い町工場”から何を学べるか?
社長就任初日にスクラップ置き場へ
「就任1年目に黒字化しないと、優秀な人材に見切りをつけられ、再建はできなくなる。P・ドラッカーの言うとおり、人は最大の財産。社員も、派遣社員も、掃除のお姉さんも、食堂の人たちも、1人も解雇しない」――06年4月に明星電気顧問に就任、6月に同社社長となった上澤信彦氏は、当時の決意をそう語る。

明星電気社長
石井 潔氏
石井 潔氏
上澤氏は生え抜きではなく、いわば“再建請負人”。自動車部品大手のカルソニックカンセイ出身で、日米のグループ会社の再建に手腕を発揮。03年には、同じ自動車部品の日興電機工業の社長に就任。その立て直しにも成功している。
「自動車部品は、品質についてもコストについても世界一厳しい業界。電機と比べても、自動車のほうが素晴らしいと思っています」(上澤氏)

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント