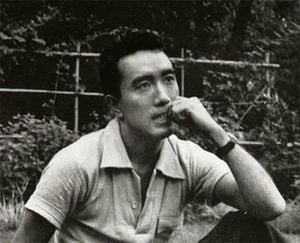「オレは3000万人を相手にしている」
――猪瀬さんと「作家・石原慎太郎」の出会いはいつですか?
あれはぼくが小学4年生の頃だったかな。記憶に残っているのは『太陽の季節』の映画ポスターが強烈だったこと。砂浜で抱き合う水着姿の男女がいままさにキスしようとしている……。1956年1月23日に芥川賞を受賞した『太陽の季節』は、早くもその年の5月に映画化されたんだけど、子ども心に不良の映画だと感じたのを覚えている。
ぼくが石原さんの小説をはじめて読んだのは高校か大学で、1960年代半ば。すでに芥川賞受賞から10年近くが経っていた。その頃、人気だったのが大江健三郎。太宰治に憧れて「自分と同じだ」と勝手に共感するような文学青年が、つぎのステップとして大江健三郎を熱心に読んでいた。当時から自分は世の中に受け入れられないアウトローだと思い込んでいる文学青年が文学の主流を担っていたわけだから、石原さんの小説はウケなかった。
ある意味で、それは当然だったと思う。文学青年に愛される作品を書いた大江健三郎と、石原さんは発想がまったく違うわけだから。石原さんは大江健三郎に対して「あなたの読者は3万人だろうけど、オレは3000万人を相手にしている」と語った。石原さんは、斜に構えてショートピースを吸う文学青年ではなく、町場の旋盤工から孤島の漁師にまでに届く小説を書こうとしていた。
「連隊旗を渡す」三島由紀夫はその才能を見抜いていた
石原さんの小説に対する考え方が分かるのが、太宰治批判。石原さんが三島由紀夫と文学について対談すると決まって「太宰はダメだ」という話題になった。三島は「冷水摩擦したり、ラジオ体操したりすれば、太宰の悩みなんて吹っ飛んじゃう」と批判した。三島も石原さんと同じで、3万人ではなく、3000万人の読者を相手にした作家だったから、相通ずるものがあった。だからこそ、三島は石原さんに「連隊旗を渡す」と語り、後継者指名した。三島は、石原さんがアウトロー気取りの文学青年だけではなく、もっと広い世界を相手にできる才能があると見抜いていた。
そこには、ほかの日本人作家が持っていなかった三島ならではの作家観がある。作家は小説も書くだけでなく、全人的な要素が必要とされると三島は考えていた。
ヨーロッパの作家ならトーマス・マンも、バルザックも、いち作家にとらわれない活動をしたわけでしょう。フランスのアンドレ・マルローは文化大臣を務めたし、ダンテも政治に参画した。チャーチルも政治家でありながら、文学的な文章を残した。彼らはアウトローではなく、社会のメインストリームを歩んできた。日本なら、大学教授だった夏目漱石や、官僚の森鴎外がそう。ただ田山花袋あたりから、弟子の女の子に手を出したとかいう話が世間を騒がせるようになって、作品そのものよりも醜聞や好奇心で読者の関心を惹くようになる。
その点で言えば、石原さんも三島もメジャーとマイナーの違いを分かっていて、小説とはなにか、作家とはどんな存在かという意識を共有していたんじゃないかな。