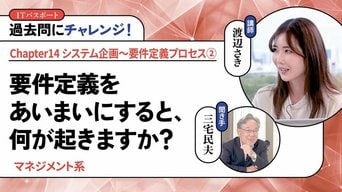イタリアのバロック期を代表する画家でありながら、傷害や恐喝、ついには殺人まで犯し、逃避行の中で鬼気迫る作品を描き続けたカラヴァッジョ。アートディレクターのナカムラクニオさんは、「逃げれば逃げるほど、ケンカをすればするほど絵画に迫力が生まれることを発見してしまったのかもしれない」という――。
※本稿は、ナカムラクニオ『こじらせ美術館』(ホーム社)の一部を再編集したものです。
生々しいリアリティ
カラヴァッジョは、光と闇の画家だ。わずかな光と膨大な闇で鑑賞者を魅了する。
描かれている作品のすべてが彼自身をモデルにしているように感じられるところも非常に興味深い。
技術的に優れているというよりは、生々しいリアリティが魅力だ。
彼は、イタリアのバロック期を代表する画家でありながら、傷害、器物破損、恐喝で裁判沙汰を起こし、少年愛を告発され、さらに殺人まで犯している。投獄と脱獄を繰り返し、逃避行の中で鬼気迫る作品を描き続けたのだ。彼自身が劇的な絵画空間を生きた男だった。
「賭けテニス」で負けて口論に
1606年、カラヴァッジョは、知人のラヌッチョ・トマッソーニという男を剣で刺し殺した。「賭けテニス」をしていた時に負け、得点について口論となりカッとなって刺したのだ。当時禁じられていた決闘を隠ぺいするためのカモフラージュだったのかもしれない。賭けた金額は、わずか1スクードと言われる。
スクードは16〜19世紀まで使われていたイタリアの通貨だが、当時依頼された絵画の支払いが200スクード程度だったことを考えると、1万円程度の遊びの賭けだったのではないか。わずかな金額の賭けで殺人を犯したカラヴァッジョが400年後、イタリア紙幣の肖像画になるなんて誰が想像しただろうか。