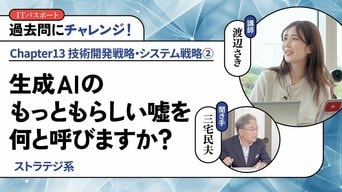男手ひとつで育ててくれた父親が記憶障害に
関東地方に住む藤原佐美さん(仮名、既婚)は現在、32歳。2歳のときに、まだ28歳だった母親が乳がんで他界してからは父親(61)の男手ひとつで育てられた。当時30歳だった父親の仕事は、転勤や国内外の出張が多かったため、北陸にある父方の祖父母の家に預けられ、週末になると父親が会いに来るという生活を送っていた。
ところが、藤原さんが小学校に入ると、61歳の祖母が若年性認知症を発症。たちまち悪化し、藤原さんにも暴力を振るうようになったため、中学に上がるタイミングで藤原さんは関東に移り、父親と2人暮らしを始めた。
それから数年後、社会に出て経理として働き始めた藤原さんは、同じ職場で15歳年上の夫と知り合い、27歳で結婚。父親と暮らしてきた家を出た。
幸せな結婚生活を満喫していた1年後、57歳になった父親から連絡が入る。
「最近忘れっぽくなって、仕事で困っている」。父親は自分の母親が若年性認知症になったことから、「自分もああなるのではないか」と恐れていたのだ。
藤原さんは、物忘れ外来を受診することを勧め、父親は検査を受けたが、結果は「異常なし」。だが、それから1年後、父親の仕事のミスが目立ち始めたため、再受診。するとわずかに脳の萎縮が見られ、長谷川式簡易知能評価スケールの点数も下がっていたため、「軽度記憶障害」と診断がついた。
その後、父親はだんだん仕事ができなくなり、59歳で退職。「若年性認知症」と診断される。
それからというもの、父親は1人で1日中ぼーっとしていることが多くなり、「これではまずい」と思った藤原さんは、主治医からの助言を受け、父親を障がい者の就労支援施設に通所させることが決まった。
不妊治療への挑戦
父親が忘れっぽくなって悩んでいた頃、藤原さんは、なかなか子どもが授からないことに悩んでいた。夫と相談し、2人で婦人科を受診したところ、藤原さんは妊娠しにくい体質であることが分かる。その頃の心境を藤沢さんはこう語る。
「父が軽度記憶障害と診断され、私が子どもを持つということは、近い将来『ダブルケア状態になるということ』です。不安はありましたが、自分の身体のタイムリミットを考え、自分を愛情たっぷりに育ててくれた父がまだ判断のつくうちに孫の顔を見せてあげたいと思い、不妊治療に取り組むことを決意しました」
不妊治療と仕事の両立は、身体的にも精神的にもつらい。薬や注射の副作用で気持ちが悪くなり、採卵前は卵巣が腫れ、お腹が張る。採卵の日は安静第一なため、仕事は休まなければならない。2度の体外受精に挑戦するも、結果は出ず、生理がくる度に精神的に大きなダメージを受けた。
それでも藤原さんは、「子どもを授かりたい!」「父に孫の顔を見せてあげたい!」という一心で耐えた。孫の姿が刺激となって、認知症の進行が緩やかになってくれたら。そんな期待も抱いていた。
そして不妊治療を始めてから3年。藤原さんが31歳になった2019年、3回目の体外受精で初めて着床。胎児は順調に成長し、男の子だということが分かる。藤原さんは、大事をとって辞職した。
ところが、31週に入ったとき、藤原さんが妊娠高血圧症になり、緊急帝王切開を行うことに。同年6月、息子は1500gに満たないほどで誕生し、NICU(新生児特定集中治療室)に入った。それから約1カ月半入院し、息子は無事退院することができた。