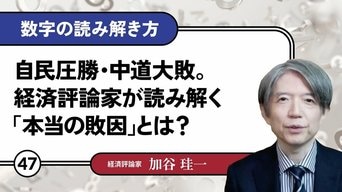中学受験が激化する中、小学校受験に挑む家庭も増えている。私立に比べ学費が格段に安い国立を併願するため、専門の幼児教育に通って対策を立てるケースも少なくない。国立大学附属小学校に7年間勤めた教員の松尾英明さんは「国立の附属小で伸びる子、伸び悩む子の家庭にはそれぞれ共通点がある」という――。
国立大学附属小学校で伸びる子、伸びない子
「入れてしまえば、あとは安心」
「偏差値の高い子が集まる学校」
多くの国立・私立小学校の受験シーズン(主に秋)になると、国立大学附属小学校(以下、附属小)についての「噂」が飛び交います。私はかつて7年間、首都圏のある附属小の教壇に立った経験があります。そこで感じたのは以下の一言に凝縮されます。
〈附属小は、すべての家庭にとって安心な学校というわけではない〉
昔も今も、附属小人気はすさまじいものがあります。保護者の中にも、「ぜひともわが子を附属小へ」と願う人が増えていますが、大事なのは、受験する家庭が「主体をどこに置くのか」という問題を本稿で述べたいと思います。
家庭が主体で関わる家庭は、見ている世界が違う
国立大学の附属小の環境を、見事に活かしている家庭・保護者にはある共通点があります。例えば、授業参観後の面談で、こんな言葉をかけてくださる保護者は1人や2人ではありません。
「あの引っ込み思案だった○○ちゃんや、やんちゃだった○○君が、こんなに育ってきた姿を見られて、本当にうれしいです。ありがとうございます」
驚くのは、視線の先にあるのがわが子ではなく、他の子たちに向けられているという点です。わが子の出来・不出来ではありません。クラスという集団の中で、他の子どもたちが育っていくことに目が注がれ、小さなプラスの変化を見逃さないのです。
こうした保護者は、人間は集団の中でこそ育つという事実を、知識ではなく実感として理解しています。なぜなら、ご自身がまさにそうした立場で、社会の中で他者と協働しながら活躍されてきた方々だからではないかと推察します。
だからこそ、「わが子が、そんな環境の一員として育っていること」それ自体が、何よりも価値あることだと考えているのです。教員としてという以前に、一人の人間として、私は何度も頭が下がる思いになりました。