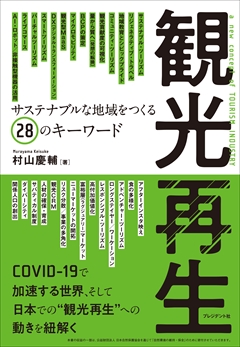デジタル化による効率化で週休3日を実現
もちろん「おもてなし」を否定しているわけではない。それは「日本の強み」といえる。ただ、それでは生産性は上がらない。休暇の楽しみ方が多様化している昨今では、これまでの価値観を一度、顧客目線で再確認・再構築していかなければ、人口減少とも相まって“ジリ貧”になることは明白であるからだ。
加えていえば、デジタルに置き換えられるところにメスを入れていくことで、むしろアナログでしかできない部分に注力することが可能となり、結果として高付加価値なサービスや体験を提供できるようになる。デジタルは決して安売りのためにあるのではないということだ。
たとえば神奈川県の鶴巻温泉にある老舗旅館の1つである「陣屋」は、女将の頭の中にあったお客様の情報をデータベース化することで、接客現場だけでなく料理場を含めたすべてのスタッフがタブレットを通じて顧客情報が確認・共有可能とするなど、デジタル化によって生産性の向上(週休3日制)とサービスレベルの底上げを同時に実現している。
観光業にとって、Go Toトラベルなどのキャンペーンによるディスカウントも必要なことではあるものの、デジタル化、それもDX(デジタルトランスフォーメーション)と呼ばれる最先端のデジタル技術を組み合わせ、いままでにない価値を創造することのほうがより重要であるということだ。
ビジネスを創り出し、業務の無駄を省く
観光分野の攻めのDXとは、デジタルデータとIT技術を組み合わせることによって生みだす新たなビジネスモデルの構築である。守りのDXとは、管理業務にAIやロボットを活用したり、非接触型サービスを導入したりすることで、経営上の無駄を省くものである。
こうした取り組みは、サステナブル・ツーリズムのためには、一事業者で行う段階から、地域全体で行う段階に入ってきているともいえる。そうした意味では、後で紹介するシンガポールの例からもわかるように、地域全体のデジタル化を底上げするような“仕組みづくり”も大切である。
そのなかで重要な役割を持つのが、DMOであり、今後の地域の観光経営を考えるうえで、地域全体の顧客管理、在庫・販売管理、販売WEBプラットフォームを一元で運用でき、自走経営できるDX体制を構築することが重要だ。
限られたメンバーのみでできることには、技術的にも、DXの精度を上げるために欠かせないデータの集積にも限りがあるからだ。
したがって、地域で一枚岩になってDXを推進していくうえでは、「DXに取り組む」という強いリーダーシップは欠かせない要素である。
地域や事業者がDXを導入する、あるいは活用したい場合、「先端技術」の中身から逆算して、課題を解決しようとしがちである。しかし、これではDXの潜在力を最大限に引きだせない可能性がある。
すなわち、「ありたい姿」や「理想のかたち」を描き、みんなでそれを共有することから始めなければならないということ。新たな価値を創造することや無駄を省くことばかりに気を取られ、肝心な経営コストが倍増し、事業継続ができなくなったり、収益性の悪化を招いてしまえば、本末転倒であるからだ。
DXを提供する側にとっても、クライアントが経営難に陥ることは得策ではない。しかし、短期的な利益確保のためにそうしたマイナス面に目をつぶる企業があっても不思議ではない。その意味でも、「ありたい姿」をきちんと明確にし、その方法論としてDXを活用するというスタンスを貫くべきだ。