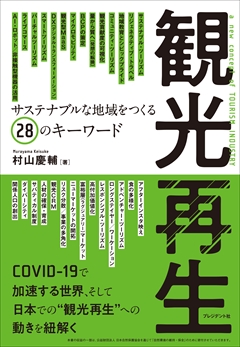「Go Toトラベル」の是非を問う声が飛び交っている。日本のインバウンド業界を牽引してきた1人である村山慶輔氏は「キャンペーンは一過性のもの。もっと本質的な議論をするべきだ。たとえば『お得意様の情報はすべて女将さんの頭の中』という状況のままでは、今後、海外の観光地とは戦えない」という──。(第2回/全3回)
※本稿は、『観光再生 サステナブルな地域をつくる28のキーワード』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。
いまだに根強い「デジタルアレルギー」
今般のコロナ禍の本質は、「10年後の未来がやってきた」ということにあると私は考えている。特に観光業やその周辺の業界は、「おもてなし」や「日本らしいホスピタリティ」といった漠然とした概念を盾に、アナログな世界が跋扈しており、お世辞にもデジタル化による効率化やサービスの磨き上げが進んでいるとは言い難い状況であった。
実際、最近もとある観光地であったことだが、DMO(観光地域づくり法人)がデジタル化を加速させようと旗を振ったところ、「デジタルじゃなく、おもてなしが重要だ!」という声があがり、遅々としてデジタル化への議論は進まなかった。
※DMOは「Destination Management/Marketing Organization」の略。官民の幅広い連携によって観光地域づくりを推進する法人を指す。従来型の観光協会・団体は調整役という性格が強い一方、DMOは観光地としての競争力を高めることに重きを置いている。
エクセルなどの表計算ソフトで管理するのならまだしも、“手書き”の宿泊台帳を使っているところは珍しくないし、“FAXや電話が主役”というところも多い。「お得意様の情報はすべて女将さんの頭の中」ということもある。そうしたアナログさが当たり前のようにある観光業界だからこそ、先のようにデジタル化へのアレルギー反応はいまだにそこかしこで見られるのである。