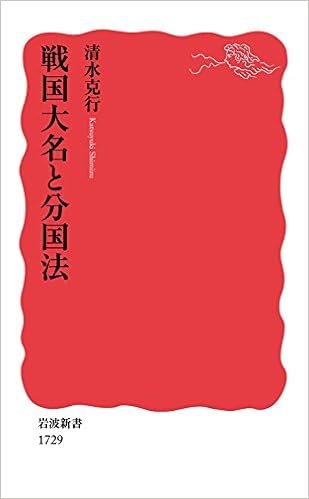「分国法」は時代を先取りしすぎていた
権力側の定める「中央の法」と、これら「田舎の法」との出会いは、早くは鎌倉後期には見られました。戦国大名たちの分国法は、これらをより本格的に法のなかに採り入れたものでした。彼らは民間の法慣習を「下から上」に汲み上げて、試行錯誤をしながら法律を自ら作ろうとしたわけですね。
たとえば江戸時代の藩は藩法を必ず持つようになりました。他人の領土を取ってナンボだった戦国時代が終われば、そうした分国法の理念は後の時代にも受け継がれた。その意味で彼らは時代を先取りしすぎていたのかもしれません。
それに織田信長でも法を作らなかったのは、庶民の慣習法に丸投げをしていたからだとも考えられます。庶民が日々の生活の中で作ってきたルールを吸い上げ、ボトムアップして成文化したものが分国法だったと考えると、「戦国大名」の苦悩や試行錯誤の先に、「戦国社会」そのものの姿が浮かび上がってくるように僕には感じられました。
「刀狩り」には「戦争に行きたくない」という民衆の思いがある
このように分国法を真正面から検証した日々は、僕にとって研究の面白さを再発見する営みでもありました。
僕が日本中世史の研究者を志す上で大きかったのは、『刀狩り』(岩波新書)の著者である歴史学者・藤木久志先生との出会いでした。
藤木先生は新潟の農村の生まれで、「ほとんどの日本人の先祖は農民だったのだから、戦国大名などよりも庶民の歴史をもっと明らかにすべきだ」というポリシーを貫いてきた研究者です。
それまでの庶民の歴史といえば、権力に追い詰められて一揆を起こし、結局は鎮圧されるというマルクス主義的な図式で描かれるものがほとんどでした。いわば「敗れ去る庶民」というイメージが一般的だったと思います。しかし、藤木先生はそれを屈折しているものと考え、実は権力に負けているように見えて、最後に大きな果実を得てきたのは民衆なのではないか、という視点で歴史を読み直したのです。
例えば教科書に載っている有名な刀狩りも、「百姓は農業に専念していればよく、戦争には行く必要はない」ということを秀吉が保証したと捉えると、「戦争に行きたくない」という民衆の思いを組み上げた法律となる。
戦争は武士たちが行ない、年貢は百姓が納める――「刀狩り」という従来は権力の圧制のように理解されてきたものを、権力と民衆のギブ&テイクの結果として捉え直す藤木先生の視点は、子供の頃からの歴史好き少年だった僕にとって衝撃的でした。