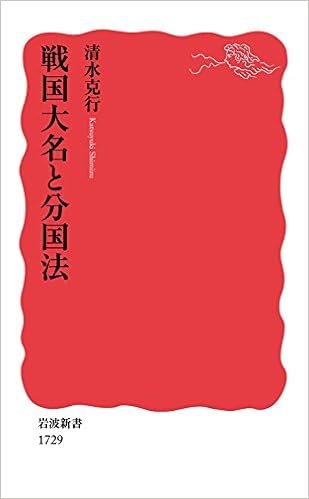教科書では説明できない「分国法のパラドックス」
高校の日本史の教科書には、「分国法」という言葉がかろうじて掲載されています。そこでは、それが戦国大名の必要条件だったとされています。独立国家を作る上で大名は法を必要とした、と説明されているわけです。
これは歴史学者の石母田正(1911-86)の学説によるものです。石母田説によれば、戦国大名の権力は、独立した「国家権力の歴史的一類型」と位置づけられます。そしてその権力は、倫理的体系や自己神格化などの宗教的イデオロギーによる支配の正当化を行わない「裸の権力」であるため、「『法』という客観的な非人格的な規範」がほとんど唯一の正当性の役割を担ったとされています。
しかし、それではなぜ、現在にはわずか10点ほどの分国法しか伝わっていないのかという疑問が湧いてきます。独立国家にとっての必須条件であれば、天下を取った織田家を筆頭に、もっと多くの分国法が伝わっていてもおかしくないと思うのが普通でしょう。
分国法について調べていて気が付くのは、実は教科書のそうした記述とは裏腹に、分国法を作った大名は全て滅びていることです。一方で織田信長のように勝ち残った者が作った法律は、今に至るまで見つかっていない。
法に縛られなかった者の方が勝ち残った
そうなると、歴史教科書の従来の説明は少し転倒していると言わざるを得ません。私はこのことを「分国法のパラドックス」として本に書きました。では、なぜ分国法を定めた大名たちは、みな滅んでしまったのでしょうか。
法律とはそれを作った権力側をも縛るものです。法を作ると領国において恣意的な処断――「俺がルールブックだ」というような支配はやりにくくなるはずです。例えば、見せしめ的に一人だけを重い罪にして、周りを震え上がらせて言うことを聞かせる、といったことはできなくなる。
戦国時代という乱世の中では、他人の領土をぶんどった者が生き残りました。その意味で分国法を作った大名は真面目というか、線の細い人物が多い印象があります。そのようにして、法に縛られなかった者の方が勝ち残ったのは歴史の皮肉でしょう。本では次のように書きました。
ただし、分国法は歴史的にまったく無意味なものだったわけではありません。日本の法制史学の基礎を築いた中田薫(1877-1967)は、かつて分国法の意義を「従来法律的に対立していた公家法・武家法・民間慣習の三者を綜合して一となした点にある」と語っています。ここでいう「民間慣習」とは、「先例」や「古法」といった有形無形の法慣習や習俗のことです。