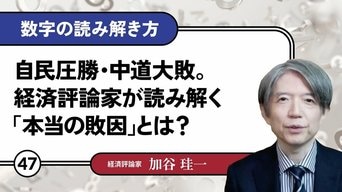前回までの記事で、世界のトヨタがマツダの開発手法をマークするに至った事件と、挑戦的な自己改革を断行せざるを得なかったマツダの経営背景を説明した。
■トヨタとマツダが技術提携に至った“事件” http://president.jp/articles/-/22041
■トヨタを震撼させたマツダの“弱者の戦略” http://president.jp/articles/-/22042
2000年代に入ると、20世紀の自動車産業を支えてきたセオリーであるプラットフォーム共用(部品共用)に限界が見え始め、自動車業界はポストプラットフォームのブレークスルーを必要としていた。マツダはフォード傘下を離脱するにあたり、その大きな課題に挑まねばならなくなった。人的にも経済的にも少ないリソースを最大限に活用して、性能の良い商品を低価格で作り出す以外に生き残る道はなかったからだ。何としても生存に不可欠な8車種を、短期間に作らねばならない。
自動車設計は膨大なファクターが絡み合い、あちらを立てればこちらが立たないことの連続だ。それを解きほぐして解決することは非常に難しい。しかしマツダの説明によると、枝分かれした川のように膨大なファクターの因果関係を整理していくと、どこかに「大河の一滴」がある。それを見つけ出し、選択して集中的にリソースを投入する。そうすると、まるでボーリングの一番ピンを倒したように全ての問題を雪崩式に解決できる糸口が見つかるという。こうした考え方に基づくモノ作り改革が「コモンアーキテクチャー」であり、それを商標化したマツダの呼び名が「SKYACTIV(スカイアクティブ)」である。SKYACTIVとは、単純にエンジンだけを指す名称ではないのだ(http://www.mazda.com/ja/innovation/technology/skyactiv/)。
大河の一滴の部分は、大きな原則を8車種全ての車両にしっかりと固定する。逆にそうでないところは大胆に変動させて車種ごとの明確な個性を生み出す。固定と変動。コモンアーキテクチャーを駆使してマツダの生き残りを賭けた開発が行われた。
この起死回生の戦略を生み出したキーマンの一人が、藤原清志専務だ。今回は藤原氏へのロングインタビューを通して、厳しい経営環境の中でどうやってコモンアーキテクチャー戦略が生まれたのかを追う。聞き手は池田直渡。
マイナーチェンジではなく、年次改良。商品をいつも最新の状態に
――マツダは今、コモンアーキテクチャーを非常に重視しているように思います。まずはその理由を聞かせてください。
【藤原】われわれみたいな小さな会社が、アフォーダブル(編注:購入しやすい価格、の意味)で、なおかつ機能の優れたクルマを作り続けていくにはこれしかないと思っています。普通ならわれわれの会社規模で言うと、多分2~3車種作れば精一杯というぐらいの規模なんですが、それが(フォードグループ離脱以来、コンパクトカーの)デミオから(北米向けSUVの)CX-9まで、あれだけのクルマを5年位の間に開発して生産できているのはコモンアーキテクチャーのおかげです。ちょっと謙虚目に言いますが「ある程度良い性能で」(笑)、アフォーダブルな値段でお客さまに提案できているかなぁと。さらに、そこまでで終わらずに、毎年商品改良をして、全てのモデルがずっと最新の状態に一斉に進化できているということまで含めて、コモンアーキテクチャーの強さなんです。
――マツダがIPM(インテリム・プロダクト・メジャーの略)と呼ぶ商品改良、つまり従来のマイナーチェンジに代わる年次改良のことですね。これからずっと、毎年改良していくルーティンになっているんでしょうか?
【藤原】ルーティン化しています。賛否両論あるんですけどね。「買い時じゃない」とかって書く人がいるので(笑)。ただやっぱり、ショールームにいらっしゃるお客さまのことを考えると、いつでも最新の状態でクルマが並んでいるというのはひとつのメリットだと思いますし、「いつ買うんだ」と考えた時、「欲しい時が買い時です」と言える状態にしたいと思っています。お客さまにとってもわれわれにとっても、小規模な会社が効率的に良いクルマを継続的に作り続けられるということがコモンアーキテクチャーの最大のメリットだと思っています。