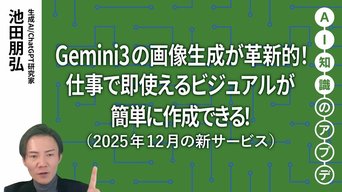※本稿は、真鍋厚『令和ひとりカルト最前線』(現代書館)の一部を再編集したものです。
人間が持つ「不要とされることの不安」
「古いバージョンになること」「無価値のレッテルを貼られること」「廃棄されること」への恐れがブラックホールのごとく渦巻いている。「誰かのお荷物になっていないか?」「役立たずと思われていないか?」「すでにリストラ候補に入っているのではないか?」……。
これをシンプルに「〈不要とされる〉という不安」と呼んだのは、社会学者のリチャード・セネットである(『不安な経済/漂流する個人――新しい資本主義の労働・消費文化』森田典正訳、大月書店)。
「要するに、〈不要〉という物理的不安の出現とともに、不安な文化的ドラマの幕があいたのだ。他者の眼前で自分を有益にして、かつ、価値ある人物に見せるにはどうしたらいいか」(同前)。
経済のグローバル化によって雇用や賃金が不安定化する中で、労働者にはこれまで以上に恒常的なフレキシビリティ(柔軟性)と学習意欲が求められ、急速な社会変動に伴うでたらめな配置転換と異業種への移行圧力に耐えなければならない。これは過去の言い方にならえば、「潰しが効く」と「自己研鑽」の必須化だ。
そんなにっちもさっちもいかない悪夢から逃れようともがく人々は、高い業績を維持し続けるハイパフォーマーや、副業・起業で高収入を稼ぐ成功者になれなくとも、「市場から必要とされる人材」として確実に残ることを願い、少しでも自身の生産性を向上させようと躍起になる。
社会から「賞味期限切れ扱い」されることの恐怖
「若い魅力的な女性」というSNS上の虚構人格で恋愛することに熱中し過ぎるあまり、自己を見失ってしまう50代女性の悲劇を描いた映画『私の知らないわたしの素顔』(2019年、フランス/ベルギー、監督:サフィ・ネブー)は、「〈不要とされる〉という不安」が作り出す自尊心の真空地帯を暴いている。
主人公が精神科医に吐露する「怖いのは死じゃない。見捨てられること」は、個人化された社会において「廃棄扱い」されることの恐怖を見事に表現している。「われわれは皆、遅かれ早かれ非生産的となり、〈不要〉の烙印をおされることになる」(前掲書)……労働市場だけでなく恋愛市場においても食品と同じく消費期限切れが待ち構えているのである。