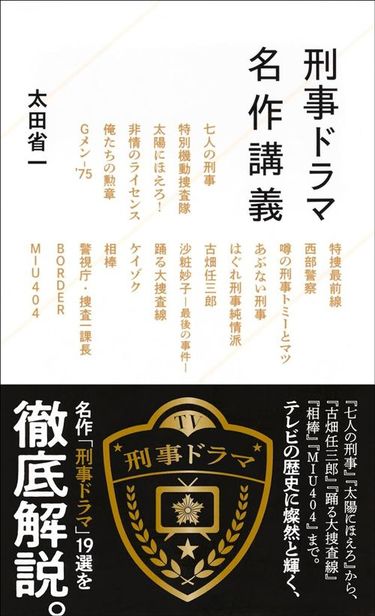古畑任三郎はなぜ拳銃を持たないのか
「普通の刑事もの」だったら引き受けなかったと語った田村正和。そうした古畑任三郎の“普通の刑事ではないところ”が端的に表現されていたのが、第1シーズンの最終話となる第12話「最後のあいさつ」だろう。
この回の犯人役は菅原文太。彼が演じる小暮音次郎は強面の警視庁警視で、古畑の上司だ。小暮は2年半前、孫娘を殺されていた。ところが被疑者として逮捕された男に対し、証拠不十分で無罪の判決が下る。
それに到底納得できない小暮は、自ら銃で男を殺す。事件の担当になったのは古畑。だが小暮には別の事件で犯行時刻には張り込みをしていたというアリバイがあった。そのアリバイをどう崩すのか? 小暮を犯人とにらんだ古畑の捜査が始まる。
そして最後、2人の対決の場面。古畑によってアリバイの矛盾を突かれ、観念せざるを得なくなった小暮は、上司としての気持ちをのぞかせながら「いいぞ、古畑。俺の負けだ」と犯行を認める。そしてこう語り出す。
「いつも思っていた。往生際の悪い犯人ほど情けないものはないって」「自分が捕まるときは誇り高くいたいもんだと」「灰原は人間のくずだ。わかってくれ。俺が法に代わって……」。
小暮がそう言いかけたとき、古畑は珍しくきっぱりとその言葉を遮る。「小暮さん、それは違います。人を裁く権利は我々にはありません。我々の仕事はただ事実を導き出すだけです」。
古畑任三郎を独自な存在にしたもの
古畑のその毅然とした態度に、小暮はようやく落ち着きを取り戻す。そして「納得がいったよ。君に拳銃は必要ない」と古畑に言う。
実はこの対決の前、古畑が拳銃を携行していないことをめぐって2人は会話を交わしていた。麻薬取引の現場に踏み込む小暮に同行させられた古畑は、拳銃の準備をしておくように言われ、持っていないことを白状する。「使いかたもわからない」と言う古畑に悪びれた様子はない。それを見て少しあきれたような小暮。
そしていま、小暮に「君に拳銃は必要ない」と言われた古畑は、「警視、最高の褒め言葉です」と喜びをあらわにする。敬礼する古畑。小暮も敬礼を返す。この小暮との一連のやり取りからは、拳銃を持たないことが古畑にとってひとつの思想であることが見えてくる。
つまり、警察官とは、拳銃による力の行使ではなく事実の解明のみによって職務を果たすべきものである、ということだ。
他の刑事ドラマであれば、拳銃を撃つことをためらい、悩む刑事はいても、最初から拳銃を持つこと自体を拒否する刑事は存在しないだろう。この思想的な“非暴力性”こそが、刑事ドラマ史にあって古畑任三郎を独自な存在にしているのである。