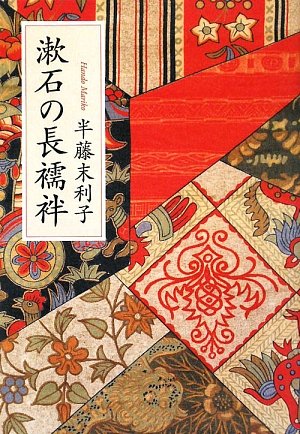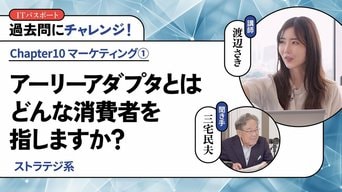いきなりこういうことを書くのはちょっと気が引けるのだが、えいっと思い切って書いてしまえば、正直なところ、私は女流作家的随筆、とでもいうようなものはあまり好きでない。いかにも、女性らしいこまやかなる感性(のようなもの)を発揮しつつ、やや古風で雅やかな語彙などを駆使しつつ、日常茶飯のことをくねくね縷述する、とでもいおうか。そういうのはなんだか鬱陶しいのである。

半藤末利子●はんどう・まりこ 東京生まれ。上智大学卒業。エッセイスト。父は夏目漱石門下の作家松岡譲、母は漱石の長女筆子、夫は昭和史研究家の半藤一利である。9歳から高校卒業まで暮らした疎開地長岡が第二の故郷となった。著書に『夏目家の糠みそ』『夏目家の福猫』などがある。
さて、ところが、この半藤末利子さんの書かれた『漱石の長襦袢』という本は、どこからどう読んでも、叙上の意味での女流作家的随筆の臭みがない。うそだと思ったら、試しにどこでもいいから本書を繙いて一つ二つ短い随筆を読んでみるがよい。じつにさっぱりとして粘らず、一言以(もっ)て之を蔽(おお)うべくんば「清爽なる文章」と評しうる。
たとえば、ここに「60年前」という好箇の小編がある。漱石の娘筆子を母に、漱石の弟子松岡譲を父にもつ筆者が、その父の郷里越後の寒村に疎開した頃のことを追憶しながら、それから60年後の感懐を綴ったもので、ちょっと漱石の「ケーベル先生」などのような上質の随筆に通うさっぱりとした、しかし滋味深い筆意を感じる。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告非表示で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント
(大杉和広=撮影)