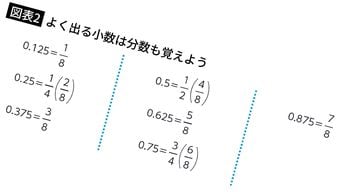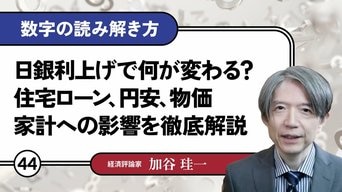どれほど自由な世の中になろうとも、自分で選ぶことができないのが家族である。特に、どんな親から生まれるかということは、自由意思から最も遠くにあるといえよう。
ここまでは、一般論だ。だが、少子高齢化が進み、しかも急激な社会変動のおかげで、世代によって個人の権利と義務に関する感覚が大きく異なる今日の日本では、こんな一般論がひどく重く感じられる。親の老いに直面して、もはや若くもないその子供が、自分に自由があると思っていたのは錯覚だと、思い知らされるからである。宿命などという古めかしい言葉が、急に切実さをもって迫ってくる。
その切実さを実感させてくれるのが、3本の中編小説を収録した本書『長女たち』だ。タイトルからもわかるように、主人公はいずれも女性で、社会的な立場はキャリアウーマン、僻地医療に生きる女医、そして家事手伝いと、大きく異なっているが、長女であり独身という点は共通している。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント