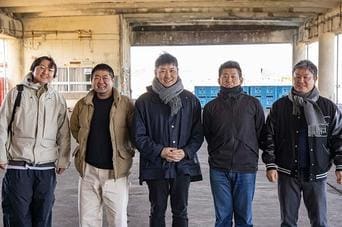意外だった郵便局内部からの情報提供
――本書は末端の郵便局員が保険契約の過剰なノルマや、自分で年賀状を買って販売枚数を稼ぐ「自爆営業」に苦しんでいるブラック企業的な現状から始まります。読み進めていくと、『ブラック郵便局』という題名が、実際には現場にとどまらない郵政全体のブラックな構造から来るものであることが、次第に明らかになっていきます。
【宮崎】取材の出発点は、局員がノルマに追い詰められていること、自死を選んでしまった局員の存在、保険のノルマを達成するために顧客のお年寄りを騙すようにして契約を結んでいるという実態に対する問題意識でした。
しかし取材を重ねる中で、それが単に一つ一つの職場の問題、単純なノルマや働き方の問題であるだけではなく、郵便局のあり方や政治とのつながりという、構造的な問題から来るものであることが分かってきたのです。まさか政治の話にまでたどり着くとは、取材を始めた当初は思ってもみませんでした。
郵便局に関する問題は西日本新聞で記事を出すたびに大きな反響があり、内部からの情報提供が多かったことも他の取材とは異なる点でした。組織の問題を追及するような記事は、その組織にいる人からすれば世間に知られたくないことですし、統制の取れた組織ほど、指摘された部分に内部で対応しようとします。そのため、内部の声が外に出てくることはあまりないのです。
3年間で1000件もの告発
ところが郵便局に関しては次々に情報が寄せられ、3年間で1000件にも上りました。現状に疑問を抱いている人たちからは、切々と綴られた長文のメールが来ることもたびたびありました。話を聞いているうちにこちらも専門用語に詳しくなってきて、自分も郵便局で働いているような気持ちになってきたほどです。
一方、内部には現状の仕組みに疑問を持っていない人、おかしいと思いながらも従うしかないと考える人もいれば、進んで仕組みに乗ることで契約件数をあげて高額のインセンティブをもらっているような人もいました。こうした人たちには、取材に行っても話を聞かせてもらえないことがほとんどでした。
職場での軋轢に苦しむ当事者の話は、やはり重みが違います。しかし「ノルマがきつい」だけではなかなか記事にはできませんし、きちんと裏付けを取らなければ郵政側から「営業妨害だ」などと言われかねません。保険勧誘で高齢の顧客を騙して契約するような法令違反の事例や、裏付けを得られる事例を積み重ねることで、結果的に構造的な問題が見えてきました。