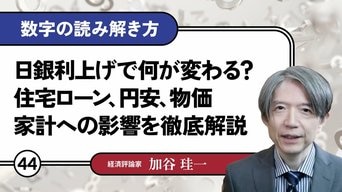“ネガティブ記事”に、社員が苦しむのがつらかった
――平井一夫氏は、2012年にソニーの社長兼CEOに就任した。当時のソニーは赤字続きで経営危機に陥っていた。平井氏はCEOへの就任内定の際に「痛みを伴う改革を断行する」と宣言(*1)。求められていたのは“会社の再生”だった。
ソニーグループCEOを務めていた約6年間でもっとも印象的だったのは、危機的状況にあった会社をマネジメントチームや社員と一緒に立て直したことでしょうか。
とくに厳しかったエレクトロニクス部門をターンアラウンドして、同時に映画、音楽、ゲームでも高い利益を出し、最終年度(2018年3月期)には10年ぶりに史上最高益を出すことができた。CEO就任時は「ソニーは大丈夫か」と危ぶまれていただけに、これは達成感がありました。
一方、苦労も多かったです。とくにつらかったのは、マスコミにネガティブな記事が出ること。たとえば14年に「VAIO」ブランドのパソコン事業を売却したときはネガティブな報道一色でした。
――当時の報道を振り返ると、実はこのとき同時にテレビ事業の分社化も発表していた。テレビ事業は10年連続の営業赤字で、累積赤字額は7900億円に達していた(*2)。分社化の目的は事業トップに権限委譲して責任を明確にすることだったが、世間はそう受け取ってくれず、「分社化は売却への布石では」という懐疑的な見方もあった(*3)(*4)。
記者からも「テレビ事業はいつ売却しますか」「いつ撤退しますか」といった後ろ向きの質問ばかりでした。経営陣は矢面に立っていいのです。私は別にいくら批判されたっていい。耐えがたかったのは、社員やその家族がネガティブな記事に晒されることです。帰宅した社員が子どもから「お父さんの会社は大丈夫なの?」「お母さんの会社がつぶれるって聞いたよ」と聞かれている姿を想像するのは本当に苦しく、つらかった。
「大量生産」「手ごろな価格」からの脱却を図った
経営再建は一夜にしてできるものではないと頭では理解していましたが、社員やその家族のために早く復活への道筋をつけなくてはいけないと焦りが募りました。
そもそもテレビを中心としたソニーのエレクトロニクス部門はなぜ低迷したのか。日本メーカーに共通する一般論でいえば、商品の魅力や価格で海外メーカーに勝てなかったことが大きいと思います。
とくに価格面は、同じ土俵で勝負しているかぎり、人件費の安い地域で生産している海外メーカーに勝てないことは火を見るより明らか。それまでといかに異なる土俵で相撲を取るか。それが当時の日本メーカーが直面する課題でした。
では、ソニーはどうだったのか。幸い、ソニーは競合と差別化できる素晴らしい技術をたくさん持っていました。より画質や音質がいいテレビを開発して、プレミアムを取れる価格で販売する戦略にシフトすれば、海外勢とマーケットシェアを競わなくても戦っていけます。それもまた明らかなことでした。
ただ、理論通りにいかないのがビジネスの難しいところです。当時はテレビの主な販路は家電量販店などの小売店でした。店頭では、いかに商品をたくさん並べて面取りできるかが売れ行きを左右します。そのため安くてもいいから台数を伸ばすことが求められたのです。
大量生産して、手ごろな価格で売っていく――。その思い込みや文化は強固なもので、社内でもかなりの議論が巻き起こりました。「台数よりプレミアム」と私が主張しても、「フルラインナップで店頭に陳列しないと売れない」「テレビはソニーのフラッグシップカテゴリー。テレビで目立てなければ他のカテゴリーにもマイナスの影響が出る」と反対意見が出て、当初はなかなかプレミアム戦略に舵を切れませんでした。