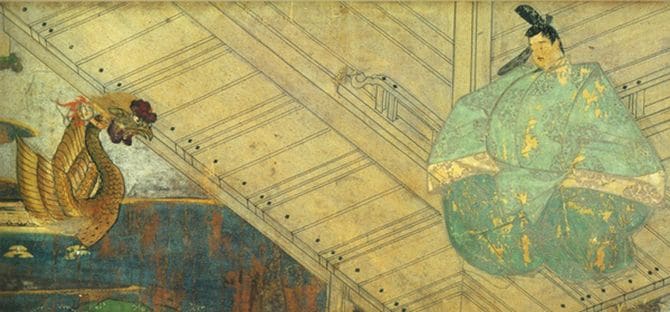藤原道長はどんな人物だったのか。埼玉大学名誉教授の山口仲美さんは「道長について描かれた『大鏡』を読むと、人に対する情愛は薄かったことがよくわかる。多くの娘をもったが、どれも『権力を握るためのコマ』としか見ていなかった」という――。(第1回)
※本稿は、山口仲美『千年たっても変わらない人間の本質 日本古典に学ぶ知恵と勇気』(幻冬舎新書)の一部を再編集したものです。
藤原道長の「強気な性格」が良くわかるエピソード
どんな人にも、不遇な時代があります。道長も、権力を掌握するまでには、不遇な時代がありました。でも、道長の逞しいところは、そんな時でも、「今に見ていろ」精神を持っていることです。
こんなエピソードが語られています。兄の道隆が関白になり、その息子の伊周は21歳で内大臣に任命されました。それに対し、道長は左京大夫でしかない。
そんな時、道隆邸で弓の競射をしていた。そこに道長がやって来て、伊周との一騎打ちになった。普通は、位の高い人に勝ちを譲るのが礼儀ですが、道長は遠慮などしない。
二番延長された競射で、まずは一矢目を放つ時に道長は唱える、「道長が家より帝・后立ちたまふべきものならば、この矢あたれ(=この道長の家から、天皇・后がお立ちになるはずならば、この矢当たれ)」と。
矢は、なんと的のど真ん中に当たった。伊周は、気後れして、矢を放ったが、的の近くにさえ行かなかった。
続く二矢目。道長は、「摂政・関白すべきものならば、この矢あたれ(=この私が、将来、摂政・関白になるのが当然ならば、この矢当たれ)」と唱えて、矢を放つ。
矢は、的が割れるほどに、同じ真ん中を射とおした。道隆は、顔面蒼白。その場は、白けに白けた。
不遇にあえいでいるのに、それをものともせず、兄一族に立ち向かっていく道長の覇気は、並外れています。道長の、こうした自負心は、若い時から見られます。