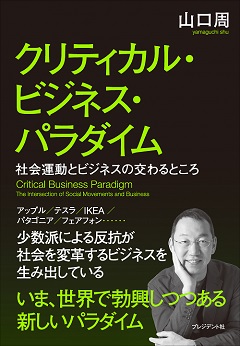マラリアを撲滅したら、次はペストが蔓延した
20世紀の前半まで、マラリアは文字通り「人類の敵」でした。マラリアのせいで毎年何万人、何十万人という人が亡くなっていたのです。このマラリアを撲滅するために開発されたのが殺虫剤DDTでした。
DDTは、本当の意味で虫を殺す歴史上最初の殺虫剤で、第二次世界大戦中には発疹チフスやマラリアの発生を抑制するために莫大な量が散布されました。
この散布は劇的な効果を上げ、たとえばスリランカでは1948年から1962年までDDTの定期散布により、それまで年間250万人いたマラリア患者の数を30人にまで激減させることに成功しています。そして、その絶大な効果を確認した世界保健機関=WHOは1955年、DDTによって地球上からマラリアを撲滅すると高らかに宣言したのです。
ところが、ほどなくしてWHOのもとに、DDTの散布地域であったボルネオで、奇妙な現象が観測されているという報告が届くようになります。DDTを散布した地域だけでペストが異常に蔓延しているというのです。
調査によってわかったのは、次のようなメカニズムでした。
DDTは極めて安定性の高い化学物質で土中でも分解されません。残留したDDTは、マラリアを媒介する蚊を撲滅したわけですが、DDTの毒性に対して耐性を持つゴキブリは体内にDDTを蓄積していきました。
解決策が新たな問題の原因にならないために
そしてこのゴキブリを捕食したトカゲはDDTにより神経を冒されて酒に酔ったようになり、簡単にネコに捕食されるようになります。ところがDDTに耐性のないネコはバタバタと死んでしまい、結果、天敵であるネズミが大量に発生し、ペストが蔓延したのです。
マラリアを媒介する蚊の根絶という側面については、DDTは文字通り絶大な威力を発揮したわけですが、別の側面ではとても大きな問題を生み出すことになってしまったのです。つまり「解決策が新たな問題の原因になっている」ということです。
では、どうすれば、このような状況が発生することを防げるのでしょうか? システムリーダーに必要な三つのコンピテンシーを用いることによって、というのがその回答になります。
システムリーダーが用いる一つ目のコンピテンシーは「より大きなシステムを捉える」能力です。複雑な状況では、人は大抵、自分に都合の良い視点から問題を捉えます。問題に関わっている人々が、それぞれの立場から問題の枠組みを捉えることで、常に「誰の視点が正しいか」という不毛な議論を引き起こすことになります。
複雑なシステム問題について関係者の共通理解を形成するために、各人が描く局所的な枠組みを包括する「より大きなシステム」を捉えるコンピテンシーがシステムリーダーには欠かせません。