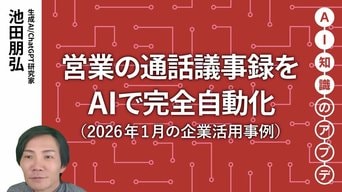アタマジラミ症が、増加に転じている。主に子どもたちがかかる皮膚病で、頭髪に寄生したアタマジラミが吸血し、頭部にかゆみが出る。保護者の誤解や虫嫌いから、差別やいじめにつながることも少なくない。
「アタマジラミの大きな問題は、子どもたちの仲を引き裂いてしまうこと。差別やいじめも相当あった。たかが『虫』で人生が変わってしまうのです」
そう、豊島区池袋保健所(東京都)の矢口昇さんは訴える。
矢口さんは2004年、全国に先駆けて保育士や教員向けの「アタマジラミ対応マニュアル」を作成した。アタマジラミの生態だけでなく、子どもや保護者への対応には十分な配慮が必要だと記した。すると、こんな電話を受けたのだ。
一家全員が「村八分」に
「これがあと1年早くできていれば」。そう涙ながらに語った電話の主は、関西の小学校教員だった。
その小学校でアタマジラミ症が発生すると、「あの子が原因だ」と、うわさが広まった。
アタマジラミ症は、不潔だから発生したり、うつったりするわけではない。どんな人の毛髪にもアタマジラミはつく可能性がある。
だが、当時は、アタマジラミは不潔な状態だからわく、飛んだり跳ねたりしてくっつく、手で触ってもうつる、不衛生な子には近寄ってはいけないなど、誤った情報が信じられていた。
結局、その地域では、感染源とされた子どもだけでなく、「一家全員が“村八分”にされてしまった」という。
「子どもには誰も近寄らず、いつもひとりぼっちだったそうです。学校に行っても無視される。とてもつらかったと思います。その家族も、地域の人たちとの交流が一切なくなった。あいさつしても返ってこないし、回覧板も回ってこない」と、矢口さんは語る。
教員は心を痛め、なんとか誤解をとこうと、学校業務が終わってから毎晩、保護者の家を一軒一軒訪ねた。しかし、アタマジラミへの誤解はなかなかとけず、問題が解決するまで1年を要したという。