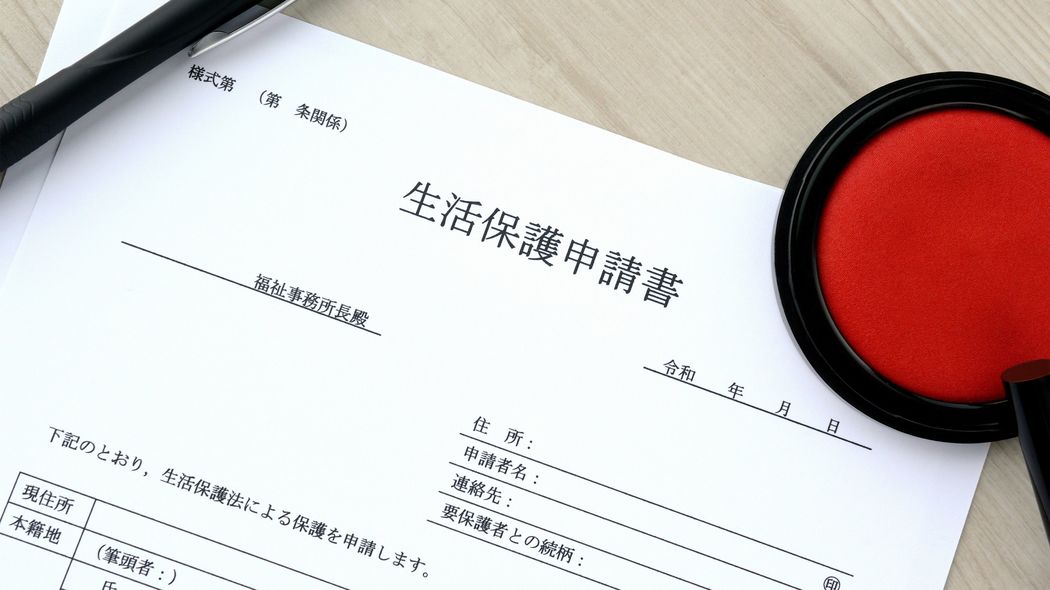祖母の貯金が底を尽き、生活保護を受給
子ども自身の目から見たとき、体験格差の問題はどのように映っているのだろうか。私たちチャンス・フォー・チルドレンがかつて教育費の支援にあたった松本瑛斗さん(当時高校生、現在20代)に、子ども時代を振り返りながら話を聞かせていただいた。松本さんの両親は彼が小学校に入る前に離婚し、その後は今にいたるまで祖母、母、弟、妹と公営住宅での5人暮らしが続いている。
――両親が離婚されてからはお母さんが家計を支えてこられたんですか。
母も最初は働いていました。でも、一人で子ども3人を育てる大変さもあって、精神障害のほうで働けなくなってしまったんですね。その頃に祖母も一緒に暮らし始めました。
祖母はずっと看護師をしていて、祖母の貯金でやりくりしていた時期もあったんですけど、その貯金も尽きてしまって。自分が中2になるぐらいまでは粘っていましたけど、その頃からは生活保護を利用するようになりました。
祖母は早めに脳梗塞をやって、今はがっつり介護が必要な状態です。一人ではいられないので、誰かが一緒にいないといけません。
「人の税金で生活させてもらう」後ろめたさ
――生活保護を利用し始めたことは、中2だった頃の松本さんご自身も知っていましたか。
僕はわかってましたね。弟と妹はまだ知らなかったと思います。人の税金で生活させてもらっているという後ろめたい気持ちがずっとありました。公営住宅に住んでいることについても、目に見える格差というか、子どものときから感じていましたね。
保護を受ける前はまだ車があったので、近くの牧場に行ったりしました。うちの母はそういうのはいっぱいやってくれたかな。大きなのは無理だけど、入場料が500円の小さい音楽のリサイタルとか、絵画展とか、昔はよく連れてってくれたなって。
――生活保護を利用して、車が持てなくなってしまったんですね。
だから、全然変わりますよね。保護を受けている間は遠出も何もなくなって。あとは、やっぱり母が病気になったということもありましたし。