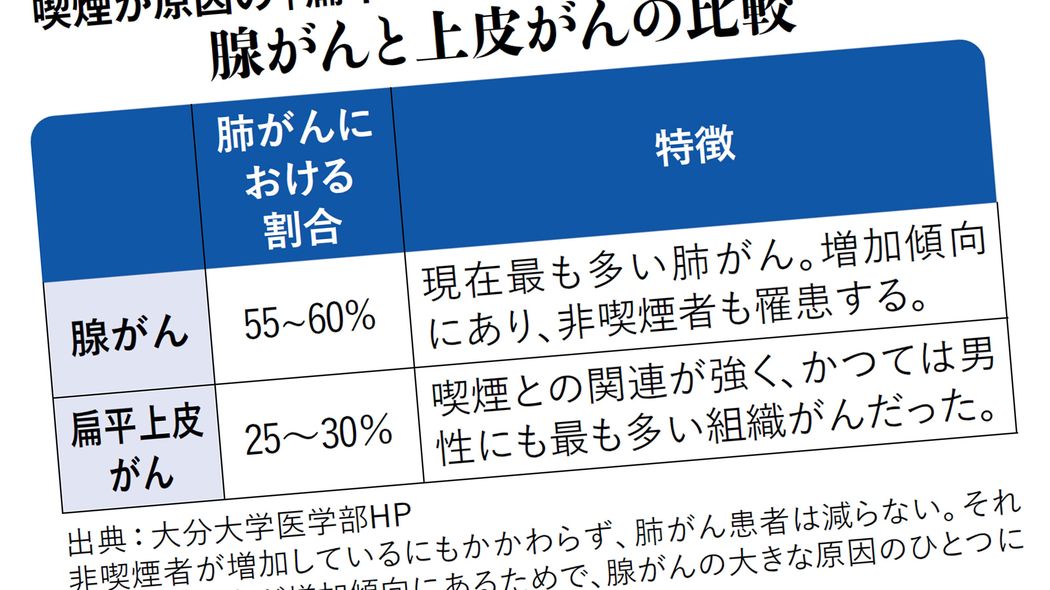喫煙者は減っているが肺がんが増えているワケ
間違い7 禁煙すれば肺がんにならない
少量の酒が「百薬の長」と評価されている一方で、タバコは、約200種類の有害物質を放出するなど、「健康被害をもたらす」というマイナス評価で一致しています。とはいえ、「百害あって一利なし」とまでは断言できないのではないかと、私は考えています。
タバコにも「一利あるかも」と考える背景の一つに、私自身のこんな経験があります。私の友人の祖父は愛煙家で、82歳で肺がんが見つかって、医師からも「手遅れ」と匙を投げられました。家族からも喫煙を反対されましたが、「タバコをやめて、ストレスをためるくらいなら」と一時やめさせられていた喫煙を再開したところ、見違えるほど元気になって、92歳の長寿を全うしたのです。
私が勤務していた医療機関に併設した老人ホームでも、高齢者を10年追跡調査しましたが、喫煙者と非喫煙者で死亡率に差はありませんでした。「タバコをやめるべきかどうか」と相談された場合、60歳よりも若い人なら、生存する可能性も考慮して、禁煙をおすすめするかもしれません。しかし、子どもが独立した人なら、余生を自由に生きる選択をしてもいいでしょう。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント