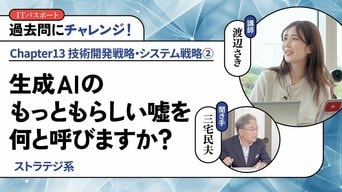青い車体が特徴の寝台列車「ブルートレイン」は2009年に引退するまで多くのファンに愛された。なぜ「ブルートレイン・ブーム」と呼ばれるほどの人気を博したのか。鉄道ジャーナリストの松本典久さんの著書『夜行列車盛衰史』(平凡社新書)より、一部を紹介しよう――。
ブルートレインだけに掲げられた「ヘッドマーク」
国鉄の夜行特急が最盛期を迎えたころ、ブルートレインは趣味の対象として大きな話題になり、東京駅や大阪駅などでブルートレインにカメラを向ける人々の姿が目立つようになってきた。東京駅では「さくら」「はやぶさ」「富士」「あさかぜ」などが発着していたが、当時、列車の先頭に立っていたEF65P形にはヘッドマークが掲げられていた。実は当時、これが唯一定期列車に掲げられていたヘッドマークだったのである。
ヘッドマークは、戦後に運転された特急「つばめ」「はと」で起用されたのをきっかけとして国鉄特急列車のシンボルとなった。1956(昭和31)年に誕生した初の夜行特急「あさかぜ」にも用意され、先頭に立つ機関車に掲げられた。その後、夜行特急は20系客車の登場でブルートレインとして発展していくが、ここでもヘッドマークは使用され、列車名にちなんださまざまな意匠のヘッドマークが誕生した。
ヘッドマークは現場からは嫌われていた
一方、列車にヘッドマークを掲出することは、業務面で大きな手間となる。特にブルートレインは長距離で運行され、始発から終点まで1両の機関車が担当することはまれだ。途中で機関車を交換するなら、ヘッドマークはそれぞれの機関車に取り付けておく必要がある。
ただし、製作費や保管場所を考えるとヘッドマークを無数につくるわけにはいかず、必要最小限の枚数で回していかねばならない。列車運行のためには、機関車、客車、乗務員などそれぞれの運用を定め、効率的に安全な運行を行っているが、ヘッドマークにもこれらと同じ扱いが必要なのだ。