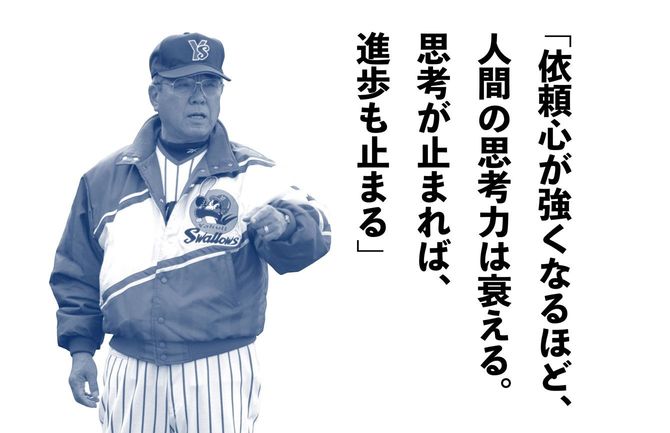「答え」ではなく、「問い」を投げかける意味
ここから髙津の試行錯誤の日々がはじまる。もともと彼が投げていたシンカーは120~125キロ程度だった。しかし、野村は「100キロくらいで投げろ」といい、同時に「150キロの腕の振りで」とつけ加えたのである。
「何度も『こんなことできないよ……』と思いながら、いろいろと握りを変え、様々な腕の振りで試行錯誤を繰り返し、ようやく1993年の夏頃から、相手打者のタイミングがずれはじめたのがわかりました。この年の日本シリーズで僕が胴上げ投手になることができたのは、間違いなく100キロ台のシンカーのおかげでした」
その後、リーグを代表するクローザーとなった髙津は、1997年には110キロ台のシンカーもマスターする。その結果、120キロ台の速いシンカー、100キロ台の遅いシンカー、そしてその中間である110キロ台のシンカーと3種類を投げ分けられるようになり、この年も日本一となった。それは、野村監督の「問い」に対する「答え」を探し求めた結果でもあった。
「いまから思えば、野村監督の言葉はいつも《答え》ではなく、《問い》でした。選手に問題を投げかけることで、自分たちで答えを探すように仕向けていました。必死に答えを探したからこそ、僕の野球人生は幸せなものとなりました。もちろん、誰に対しても同じやり方が通用するとは限らないけれど、自分も監督となった以上は選手たちにいい気づきを与えられるような《問い》を投げかけるつもりです」
相手に「責任感」を持たせ、「依頼心」をなくす
野村は、自著『野村克也全語録 語り継がれる人生哲学』(弊社刊)において、こんな言葉を遺している。
「わたしは毎日のようにミーティングを行っていたが、ひとつだけ心掛けていたことがあった。それは、『答えまでいわない』ということである。答えは、必ず選手にいわせる」
それは一体、どうしてなのか? 野村が重視したのは「責任感」であり、「考える力」だった。再び、前掲書から引用したい。
「質問に対して選手が答えを出せば、それは答えをいった選手の『責任』になる。自分でいったことには誰しも責任感を持って取り組むもので、それがいつしか、選手個々の使命感になっていく。だから、『答え』は選手にいわせるべきだとわたしは思うのだ」
そして、指導者が手取り足取り指導することで、選手に依頼心が芽生え、その結果、選手の持つ「考える力」が奪われかねないと指摘する。
「依頼心が強くなるほど、人間の思考力は衰える。思考が止まれば、進歩も止まる」
先に挙げた髙津臣吾のシンカー習得の例を思い出してほしい。野村が口にしたのは「150キロの腕の振りで遅いスライダーを投げられるか?」という「問い」だった。決して、「投げろ」という命令形ではなかった。監督からの要望には強い影響力があり、実質的には「命令」に近いものかもしれない。けれども、野村はあくまでも「問いかけ」にこだわった。
こうして髙津は、「責任感」を持って遅いスライダーの習得に励み、実際にそれをモノにしたことで球界を代表するクローザーに成長した。そこには、「依頼心」は微塵もなかった。自分自身でやるしかなかったからだ。まさに、野村の狙い通りの成果をもたらすことになった。だからこそ、野村は言うのだ。
「教えるな。質問を投げかけよ」、と。
部下を一人前に育て上げるには、「本人の依頼心を排除する」という上司の姿勢が重要になる。そのためにすべきことは「答え」を提示することではない。「問い」を投げかけることなのである。