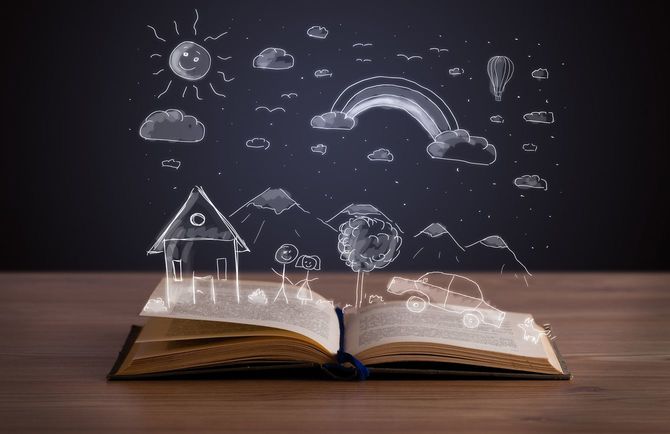丁寧に読む癖をつける「3つの問いかけ」
最初の壁は5年生だ。中学受験の勉強は、学年が変わるタイミングで急に難しくなる。5年生になると、国語に限らず、すべての教科の問題文・出題文が長くなり、内容が複雑になってくる。
例えば国語の物語文なら、自分とは違う年齢の人が主人公の話や、自分の知らない時代背景の話などを扱うようになる。すると、自分の経験に基づく勘が急に利かなくなり、「なぜ主人公がこんな行動に出たのかさっぱりわからない」「そもそもこの言葉の意味がわからない」といった状態に陥ってしまう。そして、これまで順調だった成績が急降下していくのだ。
こうした問題を解くときに必要になってくるのが、「最後まで丁寧に読む」という姿勢だ。物語文なら文中に何が書いてあるか証拠探しをするような感覚で読み進めていく癖をつけること。はじめは子供だけでは意識できないので、大人が手助けをしてほしい。
「この問題は何を聞かれているの?」
「あと何が分かれば答えが出そう?」
そうやって、大人が問いかけをしてあげることで、丁寧に読む癖がついていく。それを根気強く続けていくことだ。そうやって読み方を意識させることで、子供自身が自問自答しながら読み進めていけるようになる。
「3つの問い」は国語以外の教科でも使える
この読み方はすべての教科で有効だ。例えば算数なら、4年生のうちは問題文をパッと見ただけで、「あ、これは植木算の問題だ!」とわかり、そこに数字を当てはめるだけで正解が出る。ところが5年生になると、問題の中身が複雑になり、単に数字を当てはめるだけでは答えが出せなくなる。そして、実際の入試ではもっと内容がややこしくなり、どの解き方で解けば答えが出そうか、子供自身が持っている知識や経験を総動員させて「解き方を考え出す」ことがもっとも重要になる。
問題のシチュエーションからすると、植木算で答える問題に見えるけれど、この条件があるということは、こう解くのかもしれないな。いやいや、ここにもう一つこの条件もあるぞ。ということは、この解き方ではなくて、あっちの解き方かもしれない。と、まずは今分かっていることを書き出し、ああでもないこうでもないと手を動かしながら考える。そのときに情報のモレがないように、先に挙げた3つの問いを意識して読むことが大切だ。この読み方を身に付けてしまえば、どんな複雑な問題でも慌てることなく冷静に向き合えるようになる。
ただ、それ以前に問題なのが、そもそも言葉を知らない子が多いことだ。中学受験の指導に携わるようになって40年以上経つが、特に最近の子はその傾向が見られ危惧している。例えば算数の割合の問題に出てくる「定価」「売値」「利益」「仕入れ値」などの言葉が分からない子は意外と多い。商売の仕組みそのものが分かっていないのだ。そういう場合は、まずは言葉の意味を教えることから始めなければいけない。読解力を鍛える以前に身に付けなければいけない知識だ。