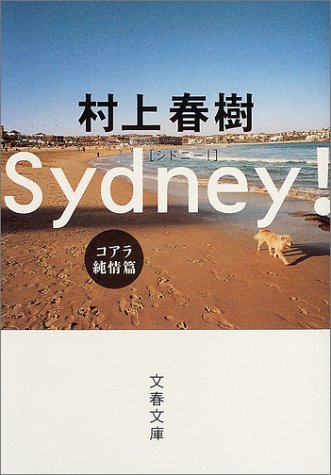ジャズよりもクラシックの評論がいい理由
おそらく春樹は、まじめなのでしょう。マラソンにかぎらず、「しろうと」として気楽に語れないことがらを正面から論じるときには、妙に力みかえる印象があります。
たとえば、クラシックやロックについては、春樹はじつに的確にコメントします。ところが、ジャズに対する態度や発言には、ときどき首をかしげたくなることがあります(『ポートレイト・イン・ジャズ』で、超有名演奏家については、わざと「本音の評価」がつたわらない書きかたをしているところとか)。
専業作家になるまで、ジャズを聴かせる店を経営していたわけですから、春樹は「ジャズのしろうと」ではありません。その自覚が、ジャズについて書くときの筆のはこびをぎくしゃくさせている気がします。
のびのびと「しろうと」の立場に身をおいて、「書くプロ」の技量を発揮したときの春樹は、じつに鮮やかに音楽を語ります。たとえば、内田光子のシューベルトを評した文章。
「彼女の演奏の枠の捉え方が、曲自体の生体枠に比べていささか大きすぎるような気がする。音楽の生活圏が、無理に拡大されているような雰囲気がある。彼女のこのニ長調のソナタの演奏はよく練られ、考え抜かれたものだし、音楽的な質も高いし、構築もしっかりしているし、音楽的表情もちゃんとあるのだけれど、そのわりに人肌の温かみが伝わってこないきらいがある。」(『意味がなければスイングはない』)
内田光子がシューベルトを弾くのを、私も生で聴いたことがあります。会場は、サントリーホールの大ホールでした。
内田は、大会場でたくさんの聴衆にむけてシューベルトを弾くことに、なんのためらいも感じていないようでした。けれども、シューベルトのピアノ曲は、内輪のあつまりか、聴衆のいない自室で演奏されることを、第一に想定して書かれています。公衆の存在がさいしょから考慮にはいっている、ベートーヴェンやショパンのソナタとはちがう音楽なのです。
内田のほかにも、大会場むけのスタイルで、シューベルトを演奏するピアニストはいます。ただし、それらの演奏家は、楽曲と相入れない弾きかたをすることを自覚し、それなりの工夫を凝らしていました。内田の演奏から、そういう配慮は聴きとれませんでした。
そのときおぼえた違和感を、春樹は的確にことばにしてくれています。内田が弾くシューベルトはさまざまに論じられていますが、こんなことをいっているのは春樹ひとりです。
ところが、小沢征爾との対談では、肩に力が入りすぎて空まわりしています。
「世界的な大指揮者と話をするのだから、あんまりしろうとくさいことはいえない」
という意識がはたらいたのでしょう。春樹は一生懸命、「くろうとっぽいことば」で語ろうとしています。そのあげく小沢に、
「僕はね、音楽を勉強するときには、楽譜に相当深く集中します。だからそのぶん、というか、ほかのことってあまり考えないんだ。音楽そのもののことしか考えない。」
といわれてしまっています。小沢は、
「プロの音楽家は、ことばで音楽を考えない」
といっているわけですから、くろうとっぽく見えるようにことばをもちいてきた春樹は、はしごをはずされたも同然です。