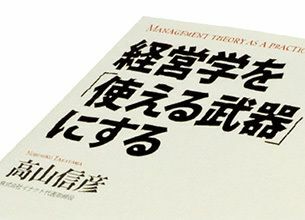いつもはビジネス書など時間のムダだとばかりまったく読まないのだが、発行元が新潮社とは珍しく、思わず手に取ってみた。体裁は絵に描いたようなビジネス書だ。著者は企業内研修講師。帯の写真を見るかぎり、よくいるタイプのコンサルタントのように見える。経歴も超高学歴でも外資系戦略コンサルティングファーム出身者でもない。しかし、深く納得させられてしまったのだ。この講師なら古い体質に苦しむ日本企業は劇的に変われるかもしれない。
研修をはじめるにあたり、受講者は経営学の古典を読むことを強要される。マイケル・ポーターの『競争優位の戦略』や『ビジョナリーカンパニー』などだ。経営学を読むことを趣味にしているような人からみるといささか古臭く、現場主義のビジネスマンにとっては時間のムダと感じるような本だ。
そのうえで著者はPPM(プロダクトポートフォリオマネジメント)やマーケティングの基本的STP-4Cなどを解説する。あまりに古典的で呆れるほどだ。しかし、これは「準備編」の一部なのだ。ここでツールを統一することで、受講者共通の基盤をつくるのが目的のようだ。
「実践編」で研修の風景は一転する。受講者たちは詳細な業界セグメント分析を苦労してつくりあげることになる。VOCと呼称される顧客の声を聞くために日本中を駈けずり回らされる。業務改善などのHowではなく、そもそも自分は何をするべきかのWhatを深く考えるよう追い込まれる。いい年をした経験豊富なおじさんたちの悲鳴が聞こえてくる。
じつはこの「実践編」では大手造船会社の常石造船を中核としているツネイシホールディングスをケーススタディとして取り上げている。受講者の実名や役職、現実に進行したプロジェクト、財務内容や企業統合のプロセスまで、あまりに生々しく赤裸々なケーススタディで、読んでいて心配になるほどだ。

2004年から11年にかけてツネイシの造船部門の売り上げは倍増し、利益は6倍になった。その原動力となったのは新製品、全長229メートルのカムサマックス級という船だった。それまでは全長225メートルが日本の港湾に接岸できる最大サイズだと思われていた。しかし『競争優位の戦略』を3回読んだツネイシの芦田さんは、著者に怒られながらも、全国の港湾を歩き回り、229メートルでも接岸できることをつきとめたのだ。
このように書くと例外的な美しい成功物語に見えるかもしれない。しかし、東レやJR西日本、みずほフィナンシャルグループなどの実例も紹介されていて、この研修が再現性と応用性があることを納得させられる。小説のようにストーリーとして読める経営書という仕上がりはさすが新潮社。ネット記事などにはない味を出していてそつがない。