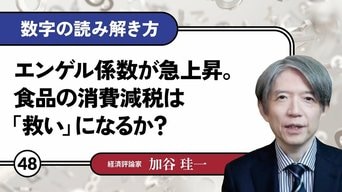開園日未明、園内には喧騒と振動が響いていた
1955年7月17日日曜日午前4時――。ウォルト・ディズニーは、この数時間というもの、パークの中を所在なげにうろついていた。誰も助けを必要としていないようだった。というより、ウォルトひとりの助けで事足りるようには見えない。
辺りには数百人もの人間が、真っ白な照明の光の下、のこを引き、ペンキを塗り、ハンマーを打ちつけ、上げ下げするフォークリフトの間をぬって、人形をあっちに置いたりこっちに置いたりしている。喧騒は延々途切れることがなく、戦時中の軍需工場さながらの振動が響いていた。
みなが160エーカー(約64万平方メートル)の大都市をつくりあげようと、最後の仕上げにかかっていた。なかには、これから大急ぎで始める、という作業もあった。2年前まではオレンジの木以外何もなかったこの南カリフォルニアの土地に、「遊園地」などというありきたりの言葉では言い表せないほど斬新なものが現れようとしていたのだ。
塔が建ち並ぶおとぎ話の城の周辺には、1世紀前のアメリカ西部の風景や、危険に満ちたジャングルの川を再現したエリアが広がっていた。そこでは、ロケットで月へひとっ飛びし、ガレオン船に乗ってピーター・パンのネバーランドを訪れ、若き日のマーク・トウェインさながらに、船尾外輪船(後ろに大きな輪がついた船)でミシシッピ川を下ることもできる。
まだ誰も体験していないさまざまなアトラクションの周りには、本物の蒸気機関車が走っていた。すでにボイラーには火が入り、シュッシュッポッポッと音を立てながら、間近に迫ったデビューを今か今かと待っている。
「ウォルトが左の眉を上げたら、まずいぞ」
はるか向こう、闇に沈む田園地帯を見やると、広報部の人間たちが、この新たな遊園地「ディズニーランド」への道を指し示す標識を立てようとしていた。
この国の生みの親であるウォルト・ディズニーは、この夜ばかりはバスローブ(ランド内をうろつくときのおなじみの格好だった)を着ていなかっただろう。緊張しているときにいつもするように、心を落ちつけようと何かしらの作業に手を染めていたはずだ。
当然、ウォルトは緊張していた。不安はときとして怒りを呼ぶ。もっとうまくやれたのにと思うことが山のようにあった。窓枠のそこかしこから、あわてて塗ったペンキが垂れ落ちているのを目にして(ウォルトの目は些細なことも見逃さない)眉をつり上げたウォルトに、部下たちは嵐がやってくるのを覚悟しただろう。
ジャングルクルーズの初代船スキツパー長のひとりだったビル・サリバンもこう言っている。「みんな知ってたよ。ウォルトが左の眉を上げたら、まずいぞってね」