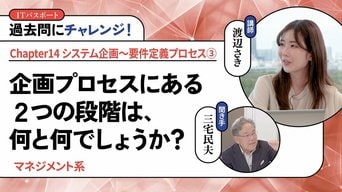謀略とは、基本的に知恵で戦う類のものであり、涼やかな頭脳労働のイメージが強い。ところが『三十六計』には、仕掛ける側が、いわば体育会系的な汗臭い努力をせざるを得なくなるという、面白い謀略があるのだ。
それが「無中生有(むちゅうしょうゆう)」。具体的には、次のように説明されている。
「無いのに有るように見せかけて敵の目をあざむく。しかし、最後まであざむきとおすことはむずかしいので、いずれ無から有の状態に転換しなければならない。要するに、仮のかたちで真の姿を隠蔽し、敵を錯覚におとしいれること」

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント