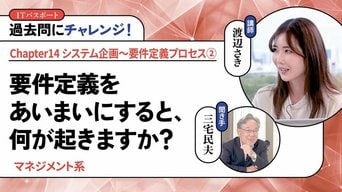人や組織には、共通の外敵がいれば一致団結し、いなくなると内部抗争に明け暮れる、という面白い傾向がある。
第二次世界大戦下で結ばれた、「エルベの誓い」など、その典型例の一つだろう。
時は1945年4月25日、ファシズム打倒を旗印に別々に進軍していたアメリカとソ連の軍隊が、エルベ河畔で合流を果たした。このとき両国の軍隊は、両国が協力して、今後は二度とこのような戦争を起こさない、と誓い合ったのだ。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント